
執筆: Leverages Global編集部 (ライター)
監修: 濱川 恭一 (行政書士)
人手不足解消の切り札として注目される特定技能制度ですが、「1号」と「2号」の違いを正しく理解できているでしょうか。この2つの区分は、在留期間や家族帯同の可否といった点で大きく異なり、企業の採用計画にも深く関わります。
この記事では、特定技能1号と2号の違いを徹底比較し、それぞれの取得方法も詳しく解説します。長期的な外国人材の活用を考える上で、ぜひ参考にしてください。
外国人採用ならLeverages Global
外国人採用をもっと安心で簡単に、
はじめてみませんか?
支援実績多数!レバレジーズグローバルが支持される理由は、
以下サービス概要資料からご確認ください。
特定技能とは

特定技能は国内の深刻な人材不足に対応するため、2019年4月に創設された在留資格です。特に人材の確保が難しいとされる産業分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人材を受け入れることを目的としています。技能実習制度が国際貢献を目的とするのに対し、特定技能は明確に労働力の確保を目的としている点が大きな特徴です。
特定技能外国人は、専門的な知識と日本語能力を備えた即戦力として活躍が期待されています。
特定技能には1号と2号がある
特定技能の在留資格には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
1号は特定の業務をこなせる即戦力向けです。一方、2号は熟練したスキルを持つリーダー向けの資格と大別できます。どちらの資格で人材を受け入れるかによって、企業の採用計画は大きく変わってくるでしょう。そのため、特定技能制度を活用するうえで、両者の違いを正確に理解しておくことが重要です。まずは、それぞれの資格の具体的な内容について解説します。
特定技能1号
特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を持つ外国人向けの在留資格です。特定技能1号で受け入れ可能な特定産業分野は16分野です。
在留期間は通算で上限5年です。特定技能外国人は、まずは1号で日本でのキャリアをスタートさせます。
特定技能2号
特定技能2号は、「特定産業分野に属する熟練した技能」を持つ外国人向けの在留資格です。主に特定技能1号を修了した人が、さらに高いレベルの試験に合格することで移行できます。2025年9月時点で特定技能2号で受け入れ可能な特定産業分野は11分野です。
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能2号は在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば配偶者と子の帯同も可能です。企業の将来を担う中核人材としての活躍が期待できます。
参照元:出入国在留管理庁「特定技能制度」
関連記事:「特定技能で受け入れ可能な業種(職種)とは?全16分野を徹底解説【2024年版】」
特定技能1号と2号の違い
特定技能1号と2号は前述した特定産業分野の数だけでなく、技能レベルや在留期間など多数の違いがあります。
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
| 特定産業分野 | 16分野 | 11分野(2025年9月時点) |
| 技能レベル | 相当程度の知識・経験(指示があれば業務遂行可能) | 熟練した技能(自己の判断で業務遂行・指導が可能) |
| 日本語能力 | 日本語能力試験での証明が必要(N4程度) | 日本語能力試験での証明は不要 |
| 支援体制 | 企業の支援義務がある | 企業の支援義務はない |
| 永住権申請 | 申請不可 | 要件を満たせば、将来的に申請可能 |
| 家族の帯同 | 不可 | 可能(配偶者・子) |
以下では、企業が受け入れを検討する際に必ず押さえておくべき6つの違いについて詳しく解説していきます。
技能レベル
特定技能1号と2号の大きな違いは、求められる技能水準です。
特定技能1号では、実務経験のある監督者から指示を受けながら、定められた作業を的確にこなせるレベルが求められます。一方、特定技能2号では、自らの判断で高度な業務を遂行できるだけでなく、他の従業員に対して指導・監督できるほどの熟練した技能が必要です。
在留期間
特定技能1号の場合、在留期間の更新はできるものの、日本に滞在できるのは通算で最長5年までと定められています。この期間が満了すると、2号に移行しない限り日本で働き続けることはできないのです。
対して、特定技能2号には在留期間の上限がありません。3年や1年といった期間ごとに更新手続きは必要ですが、要件を満たす限り何度でも更新が可能です。よって、半永久的に日本で働き続けられます。
長期的な人材確保を考える企業にとって、この差は非常に大きいでしょう。
日本語能力
特定技能1号を取得するためには、業務上および日常生活で必要な日本語能力を証明しなくてはなりません。具体的には、「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」の合格、または「日本語能力試験(JLPT)」のN4以上への合格が求められます。
一方、特定技能2号の試験では、日本語能力を直接測る試験は課されません。2号の技能評価試験に合格できるほどの能力があれば、現場のリーダーとして必要な高度なコミュニケーション能力も既に備わっていると判断されるためです。
支援体制
特定技能1号の外国人に対しては、受け入れ企業または登録支援機関が職場や日常生活、社会生活に関する幅広い支援を行うことが法律で義務付けられています。これには、住居の確保や各種手続きの補助、相談対応などが含まれます。
一方、特定技能2号の外国人に対しては、日本での生活に十分に順応していると考えられるため、義務的支援は不要です。
永住権申請
永住権を申請するには、原則として10年以上継続して日本に在留し、かつそのうち5年以上は就労資格で在留している必要があります。
在留期間が通算5年に制限されている特定技能1号では、10年以上継続して日本に在留する要件を満たすことができません。また、特定技能1号の期間は「就労資格」としての5年にはカウントされないのです。
しかし、特定技能2号の在留資格はこの10年にカウントされます。なおかつ、特定技能2号は在留期間に上限がないため、長期間日本に滞在し続けることが可能です。そのため、「素行が善良であること」「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」といった他の要件も満たすことで、将来的に永住権を申請する資格を得られる可能性があります。
家族の帯同
家族と一緒に日本で暮らせるかどうかも、1号と2号の大きな違いです。
特定技能1号の資格では、原則として配偶者や子供を日本に呼び寄せる「家族帯同」は認められていません。単身で来日し、働くことが前提となります。
一方で、特定技能2号の資格を持つ人材は、要件を満たせば配偶者と子供を帯同することが可能です。家族と共に日本で安定した生活を送りながら、長期的にキャリアを追求できます。
家族帯同の可否は、外国人材が腰を据えて長く働く上で極めて重要な要素といえるでしょう。
参照元: 出入国在留管理庁「特定技能制度」 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)」
特定技能1号の取得方法
特定技能1号の在留資格を取得する方法は、大きく分けて2つあります。1つは技能評価試験と日本語能力試験に合格するルート、もう1つは既に技能実習生から移行するルートです。
どちらのルートを辿るかによって、必要な手続きや準備が異なります。
技能評価試験と日本語能力試験に合格する
特定技能1号を取得するための最も一般的な方法は、必要な試験に合格することです。具体的には、「技能評価試験」と「日本語能力試験」の2種類に合格する必要があります。
技能評価試験は、その分野で求められる専門知識や技能を有しているかを測るものです。特定産業分野ごとに分かれており、各分野を管轄する業界団体が実施しています。どの分野も、学科試験および写真・イラストを用いた判断試験による実技試験で構成されています。
日本語能力を測る試験は、日本語能力試験(JLPT)もしくは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)のいずれかです。国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格、または日本語能力試験(JLPT)のN4以上が求められます。ただし、「鉄道」の運輸係員と「自動車運送業」のタクシー・バスの運転手は、日本語能力試験(N3以上)の合格が必要です。
技能実習から移行する
「特定技能1号」は「技能実習」からの移行も可能です。移行するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 「技能実習2号」を良好に修了していること
- 技能実習の職種・作業内容と、移行予定の「特定技能1号」の業務に関連性が認められること
以上の要件を満たした場合、技能評価試験と日本語能力試験が免除されます。なお、「技能実習2号」を良好に修了した外国人が技能実習時と異なる分野に移行する場合は、日本語能力試験を受ける必要がありません。移行予定の特定産業分野の技能試験のみ合格すれば取得できます。
参照元: 出入国在留管理庁「特定技能制度」 出入国在留管理庁「分野別情報」
特定技能2号の取得方法
「特定技能2号」を取得するためには、特定産業分野ごとに定められた試験に合格しなければなりません。また、実務経験も必要です。一般的には、特定技能1号から2号へステップアップします。
- 特定技能1号で実務経験およびリーダーとしての経験を積む
- 試験に合格する
- 在留資格を変更する
まずは、「特定技能1号」として日本国内の現場で数年間働きながら、その分野での実務経験をしっかりと積みます。あわせて、単なる作業員としてだけでなく、複数の従業員を指導・監督する班長や副店長、現場リーダーといった管理者としての経験を重ねます。
その後、各分野で実施される「特定技能2号評価試験」などを受験。合格したら、出入国在留管理庁に「在留資格変更許可申請」を行います。
なお、各分野で定められている要件は以下のとおりです。
<ビルクリーニング>
| 技能水準 | ・「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」または「技能検定1級」 |
| 実務経験 | ・特定建築物での清掃または登録された専門業者で、複数の作業員に指示を出したり、作業の進み具合を管理したりする「現場監督」や「リーダー」としての経験がある |
<工業製品製造業>
| 技能水準 | ・「製造分野特定技能2号評価試験」および「ビジネス・キャリア検定3級」 ・「技能検定1級」 |
| 実務経験 | ・日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場での実務経験 |
<建設>
| 技能水準 | ・「建設分野特定技能2号評価試験」「技能検定1級」または「技能検定単一等級」 |
| 実務経験 | ・建設現場において複数の建設技能者を指導しながら、工程を管理する班長としての実務経験 |
<造船・舶用工業>
| 技能水準 | ・「造船・舶用工業分野特定技能2号試験」または「技能検定1級」 |
| 実務経験 | ・複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験 |
<自動車整備>
| 技能水準 | ・自動車整備分野特定技能2号評価試験」または「自動車整備士技能検定試験2級」 |
| 実務経験 | ・地方運輸局長の認証を受けた工場での実務経験 |
<航空>
| 技能水準 | ・「航空分野特定技能2号評価試験」または「航空従事者技能証明」 |
| 実務経験 | ・空港グランドハンドリング:空港グランドハンドリングの現場において技能者を指導しながら作業に従事した実務経験 ・航空機整備:航空機整備の現場において、専門的な知識・技量を要する作業を実施した3年以上の実務経験 |
<宿泊>
| 技能水準 | ・「宿泊分野特定技能2号評価試験」 |
| 実務経験 | ・宿泊施設で複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、 レストランサービスといった宿泊サービスの提供に係る業務に従事した実務経験 |
<農業>
| 技能水準 | ・「宿泊分野特定技能2号評価試験」 |
| 実務経験 | ・宿泊施設で複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、 レストランサービスといった宿泊サービスの提供に係る業務に従事した実務経験 |
<漁業>
| 技能水準 | ・「2号漁業技能測定試験」および「日本語能力試験(N3以上)」 |
| 実務経験 | ・漁業:漁船法の登録を受けた漁船で船長や漁労長の補佐役または作業チームのリーダーとしての実務経験 ・養殖業:漁業法および内水面漁業の振興に関する法律に基づいて行われる養殖業の現場で、養殖管理者の補佐役または作業チームのリーダーとしての実務経験 |
<飲食料品製造業>
| 技能水準 | ・「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」 |
| 実務経験 | ・飲食料品製造業分野で、複数の作業員に指示を出したり、工程の管理をしたりする管理者としての実務経験 |
<外食業>
| 技能水準 | ・「外食業特定技能2号技能測定試験」および「日本語能力試験(N3以上)」 |
| 実務経験 | ・食品衛生法の営業許可を受けた飲食店で、アルバイトや他の従業員(外国人スタッフを含む)に指導・監督しながら接客をする副店長やサブマネージャーとしての実務経験 |
上記のとおり、特定技能2号の在留資格を取得するためには、分野ごとに定められた「熟練した技能」を持っていることを証明しなくてはなりません。
参照元: 出入国在留管理庁「特定技能制度」 出入国在留管理庁「分野別情報」
まとめ
特定技能1号と2号は、求められる技能レベルや待遇が大きく異なる在留資格です。特定技能1号は、一定の技能を持つ人材を最長5年間受け入れるための入り口であり、特定技能2号は熟練した技能を持つ人材に無期限で活躍してもらうための上位資格と位置づけられます。
特に在留期間の上限がなく家族の帯同も可能になる特定技能2号は、外国人材にとって大きな魅力です。企業にとっても、育成した優秀な人材に長く定着してもらえるというメリットがあります。
1号と2号の違いを正しく理解し、外国人材に明確なキャリアパスを示すことは、優秀な人材の確保および企業の人手不足解消のために不可欠といえるでしょう。
Leverages Globalでは、特定技能人材のご紹介及び採用支援が可能です。特定技能含む、外国人採用をご検討中の企業様はお気軽にご相談下さい。

サービスを運営する中でよく伺うお悩みや質問に対して、真摯に向き合いながらも、分かりやすく、すぐに役立つコンテンツ発信を目指しています。





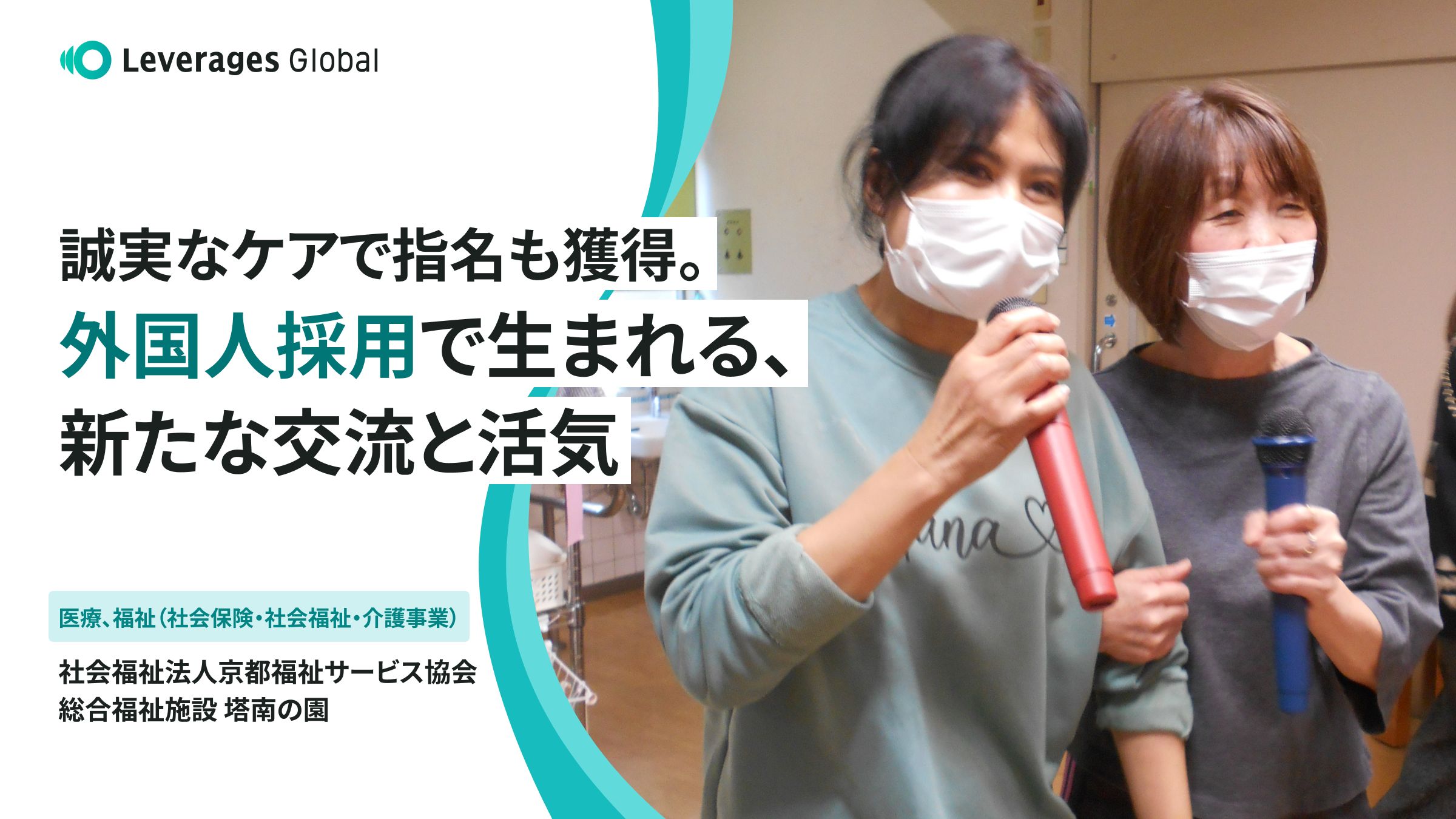
.png)





