
執筆: Leverages Global編集部 (ライター)
監修: 濱川 恭一 (行政書士)
「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は、主にオフィスワークや技術職、通訳などの仕事に就くために必要な在留資格です。幅広い企業で雇用できる一方で、外国人本人の学歴や職歴と関連性がない業務や単純労働とみなされた場合には、不許可となるケースもあります。
この記事では、初めて技人国ビザを申請する企業の担当者の方もポイントが掴みやすいよう、許可・不許可の事例を紹介します。また、取得要件や任せられる業務内容、採用時の注意点などもできるだけ分かりやすくまとめました。ぜひご一読いただき、外国人採用の検討にお役立てください。
外国人採用ならLeverages Global
外国人採用をもっと安心で簡単に、
はじめてみませんか?
支援実績多数!レバレジーズグローバルが支持される理由は、
以下サービス概要資料からご確認ください。
目次
在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、通称「技人国(ぎじんこく)」とも呼ばれ、外国人を日本で正社員雇用するうえで最も一般的な在留資格です。卒業後に日本企業に就職する外国人留学生の9割が取得するといわれています。
オフィスワークを中心に、大学で学んだ分野やそれまでの仕事の経験、言語能力、グローバルな知識を活かして働くことが可能です。5年・3年・1年または3ヶ月と在留期限が設けられていますが、更新の制限はありません。
営業・マーケティング・クリエイティブといった“総合職”の範疇の業務を幅広く行える一方で、業務内容や外国人の経歴によっては申請許可が下りない場合もあるのです。
外国人は就労が許可された在留資格がなければ、日本で働くことはできません。そのため、「技術・人文知識・国際業務」を取得できる人材を見極め、雇用する必要があるでしょう。
ここでは、在留資格「技術・人人文知識・国際業務」で行える仕事と禁止されている仕事をそれぞれ紹介します。
「技術・人文知識・国際業務」で行える業務
在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、「技術」「人文知識」「国際業務」の3分野の職種で働くことが可能です。
ここでは、具体的な職種を紹介するので、自社で外国人に任せたい業務が当てはまる場合は「技術・人文知識・国際業務」での採用を検討してみましょう。
なお、外国人の学歴や前職での年収、資格によっては高度人材となり、在留資格「高度専門職」のほうが相応しいこともあります。
「技術」分野の職種一覧
「技術」分野には理学・工学・自然科学など、いわゆる理系分野の技術や知識を要する職種が該当します。
- システムエンジニア
- ソフトウェアエンジニア
- CADオペレーター
- プログラマー
- 建築士
- 航空整備
- 機械の設計や開発業務
- 機械工学関連の技術者
- 情報セキュリティーの技術者
- 土木や建築における研究開発や設計の従事者
- ゲーム開発におけるシステム設計や運用保守の従事者
上記以外にも、専門的な技術や知識を要する理系職種であれば、対象になる可能性があるでしょう。
システムエンジニアやプログラマーといったIT人材は売り手市場であり、外国人材の獲得競争が進んでいます。詳細は「外国人エンジニアの採用ノウハウ!日本語レベルの目安や離職を防ぐ工夫」の記事をご覧ください。
「人文知識」分野の職種一覧
「人文知識」の分野に該当するのは、法律学や経済学、社会学、心理学などの人文科学の知識を活かせる職種です。
- マーケティング
- コンサルタント
- 企画
- 営業
- 経理
- 会計
- 法務
- 人事
- 総務
- 商品開発
- 広報
一般企業の“総合職”に含まれるオフィスワークの大半は、人文知識を活かせる職種に分類されます。なお、事務職の場合は、電話対応やデータ入力のみの業務では「技術・人文知識・国際業務」は許可されません。あくまで、主な業務が人文科学の知識を要するものである必要があります。
「国際業務」分野の職種一覧
「国際業務」分野に該当するのは、海外の文化を基盤とする思考や感受性を活かせる職種です。
- 通訳
- 翻訳
- インテリアや服飾のデザイナー
- 語学教師(民間企業)
- 貿易関係
- 通訳に専従するホテルマン
- 商品開発
通訳や翻訳のような分かりやすい職種に加えて、グローバルな思考や感性を要するデザイナーも国際業務分野の職種に含まれます。
「技術・人文知識・国際業務」で行えない単純労働とは
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人は、専門知識や技術を要する業務のみが認められています。そのため、「単純労働」と称される業務に従事させることはできません。
「単純労働」と書くとあまり気持ちいい響きがしませんが、「反復継続性の高い仕事」「専門知識がなくてもできる仕事」「知力より体力を必要とする労働」と言い換えることもできます。
一例として以下のような作業が挙げられます。
- レジ打ち
- 接客
- 清掃
- 警備
- 小売店での販売
- 土木作業
- 工場の組み立て作業
- ドライバー
ただし、入社後の研修の範囲であれば、単純労働が条件付きで認められる場合もあります。判断は出入国在留管理庁の審査にゆだねられるため、少しでも単純労働が発生する場合は、採用前に必ず行政書士に相談しましょう。
「技術・人文知識・国際業務」以外の在留資格については「在留資格29種類を一覧で紹介!就労の可否や注意点をわかりやすく解説」をご覧ください。
「技術・人文知識・国際業務」の申請の手続き
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請の流れは、外国人の状況によって異なります。申請をスムーズに進めるためにも、企業が流れを理解しておくことが大切です。
海外にいる外国人を招へいして採用する場合の手続き
採用予定の外国人が海外にいる状況で、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を申請する流れは以下の通りです。
- 企業が外国人と雇用契約を締結する
- 企業がオンラインもしくは入管で「在留資格認定証明書交付申請」を行う
- 「在留資格認定証明書」が発行されたら、外国人本人に送付する(オンライン申請した場合は、電子メールを転送可能)
- 外国人本人が日本大使館に査証(ビザ)を申請する
- 外国人本人が来日し就労を開始する
なお、在留資格に関する申請はオンラインでも可能です。オンラインで「在留資格認定証明書交付申請」を行えば、受け取った電子メールを海外に住む外国人本人に転送できるため、海外郵送の手間や時間、費用がかかりません。
企業がオンライン申請を利用するためには、所在地を管轄する地方出入国在留管理局で利用申出を行い、承認を受けます。審査の結果承認されたら、オンライン申請で用いる「在留申請オンラインシステム」の利用が可能です。各種書類はPDFで添付して提出します。
在留資格認定証明書交付申請の必要書類
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請に必要な書類は以下のとおりです。
なお、書類は企業カテゴリーごとに異なるので、本記事では「カテゴリー3」に該当する企業が外国人を雇用する際に必要な書類を紹介します。新設会社の場合は「カテゴリー4」に該当し、提出書類が増えるので、出入国在留管理庁のWebサイトを確認してみてください。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 証明写真(4cm×3cm)
- 返信用封筒
- 企業カテゴリーを証明する書類(カテゴリー3の場合は前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し)
- 労働条件通知書もしくは雇用契約書の写し
- 学歴を証明する文書(大学等の卒業証明書またはこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書)
- 職歴を証明する文書(在職証明書など関連する業務に従事した期間を証明する文書)
- 登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする文書
- 直近の年度の決算文書の写し
外国人本人が用意する書類もあるので、採用が決まった時点ですぐに対応できるよう手配しましょう。
同業種で働く外国人を採用する手続き(転職)
すでに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を所持している外国人を中途採用する場合、基本的に在留資格申請は不要です。
ただし、後から「外国人の経験では自社で働くことができなかった」「自社の業務は技術・人文知識・国際業務の要件を満たさなかった」といった問題が発生するのを防ぐために、「就労資格証明書交付申請」を行うこともできます。
「就労資格証明書交付申請」とは、外国人の経歴と就労先の情報を照らし合わせ、実際に就労が可能か確かめる手続きです。申請は外国人本人が行います。
また、もし外国人の在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留期限が迫ってる場合は、入社後すぐに「在留期間更新許可申請」を行ってもらうと安心です。
異業種で働く外国人を雇用する手続き(転職)
異業種で働く外国人を中途採用をする際は、在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に切り替える必要があります。
この場合に行う手続きが「在留資格変更許可申請」です。年度末は審査が混み合うため、申請してから実際に在留資格が降りるまで数ヶ月かかる場合もあるので注意しましょう。この手続きも外国人本人が行うのが一般的です。なお、外国人本人がマイナンバーカードを持っている場合は、自らオンライン申請を行うことも可能です。
在留資格変更許可申請の必要書類
ほかの在留資格から「技術・人文知識・国際業務」に変更する際の必要書類は以下のとおりです。
- 在留資格変更許可申請書
- 証明写真(4cm×3cm)
- パスポート(提示)
- 在留カード(提示)
- 企業カテゴリーを証明する書類(カテゴリー3の場合は前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し)
- 労働条件通知書もしくは雇用契約書の写し
- 学歴を証明する文書(大学等の卒業証明書またはこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書)
- 職歴を証明する文書(在職証明書など関連する業務に従事した期間を証明する文書)
- 登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする文書
- 直近の年度の決算文書の写し
異業種からの転職の際は、在留資格の該当性をよりしっかり審査されるため、書類を適切に提出することが重要です。
留学生を新卒採用する場合
留学生は在留資格「留学」を持っているため、「技術・人文知識・国際業務」を取得するには「在留資格変更許可申請」が必要です。必要書類は、異業種から転職をする際と変わりません。学歴を証明する書類を必ず提出しましょう。
参照元: 出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」 出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」
外国人が「技術・人文知識・国際業務」を取得する要件
外国人が在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 学歴や職歴と業務内容に関連性がある
- 海外の大学・日本の大学・日本の専門学校卒業の学歴
- 報酬や待遇は日本人と同等以上である
- 雇用企業の経営状態が安定している
- 特定の機関との継続した契約がある
以下で詳しく見ていきましょう。
専攻や職歴と業務内容に関連性がある
外国人がこれまで教育機関で学んできた内容や経験してきたことが、「技術・人文知識・国際業務」で行う業務内容と関連している必要があります。
外国語に関する業務(翻訳・通訳、語学教師など)は、学んできた内容はほぼ問われません。しかし、それ以外の仕事をする場合は、専攻と業務内容の関連性が重要です。
「「技術・人文知識・国際業務」を申請する際のポイント」の項目で詳しく解説しますが、最終学歴が大学卒業よりも、専門学校卒業のほうがより厳しく審査されます。
海外の大学・日本の大学・日本の専門学校卒業の学歴
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得には、以下の学歴が求められます。
- 日本もしくは海外の大学を卒業(学士号以上を取得)※短大卒含む
- 日本の専門学校を卒業(専門士または高度専門士を取得)
なお、以上の学歴を満たしていなくても、実務経験の要件を満たしていれば在留資格の取得が可能です。「技術」「人文知識」分野は10年以上、「国際業務」分野は3年以上の実務経験があれば、要件を満たせます。
報酬や待遇は日本人と同等以上である
外国人が日本企業に不当な扱いで雇用されることを防ぐため、多くの在留資格の取得要件に「報酬や待遇は同じ仕事をする日本人と同等以上」という項目があります。「技術・人文知識・国際業務」も例外ではありません。外国人だからという理由だけで賃金を下げると、在留資格が不許可になる可能性が高いでしょう。
なお、業務に制限があったり勤務時間が少なかったりする場合は、正当な理由として賃金差が認められます。
外国人にも日本人同様「労働基準法」「最低賃金法」などの労働関係法令が適用されるので、公平な人事管理を心掛けましょう。
雇用企業の経営状態が安定している
企業の経営状態も審査項目の一つです。国として外国人に就労資格である在留資格「技術・人文知識・国際業務」を付与し、一定期間の在留を許可するからには、長く安定して働いてもらわなければなりません。
申請時に提出する資料で、「経営状態が不安定」と判断された場合、外国人の在留資格取得が認められない可能性があります。
特定の機関との継続した契約がある
外国人の在留資格「技術・人文知識・国際業務」の審査において、雇用契約の形態は重要ではありま せん。契約社員であっても、ある程度継続した契約があれば在留資格が許可される可能性が高くなります。
関連記事:「外国人を雇用するには?入社前・入社後の手続きと必要書類」
「技術・人文知識・国際業務」を申請する際のポイント
ここでは外国人向け人材紹介サービスの経験をもとに、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請する際に覚えておきたいポイントをご紹介します。
観点は誰が・どこで・どのような業務に従事するのか
審査をパスするためには「誰が」「どこで」「どのような業務に従事するのか」の3点を全てクリアする必要があります。
「誰が」とは外国人の学歴・経歴・素行。「どこで」とは企業の規模・安定性・雇用実績。「どのような業務に従事するのか」とはそのまま業務内容を表します。これら3点のうち、いずれかひとつが要件を満たさなかった時点で、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することはできません。
大学の専攻と業務内容の関係性はそこまで重視されませんが、専門学校卒業者の場合は、厳しく審査されるでしょう。
企業規模・安定性については、決算書類上で債務超過になっていなければ、それほど気にする必要はありません。しかし、非上場の中小企業の場合は上場企業より細かく審査されます。
工場や飲食店を経営している企業の場合、採用後の単純労働を疑われる可能性も。
不安がある場合には後述する「雇用理由書」を作成し、「誰が」「どこで」「どのような業務に従事するのか」、その人物を採用する必要性を明確にしましょう。
学歴と業務内容の関連性はどれくらい重視される?
「技術・人文知識・国際業務」の要件のひとつに、学校で学んだ内容と業務の関連性があります。それでは、たとえば文学部や歴史学部の学生は営業職やマーケティング職に就けないのでしょうか?
実際のところ、大学の専攻と業務内容の関連性はかなり緩やかに判断されるため、業務に直結しない学部を卒業していても採用できる可能性は十分にあります。特に、1、2年生時に教養科目を履修している場合、専攻科目と直接関係しない業務であっても認められる場合が多いです。
一方で、専門学校を卒業している場合は業務内容と専攻について明確な関連性が求められます。ただし、2024年2月には、特定の専門学校(文部科学省の職業実践専門過程の認定校)に関して、業務と専攻の関連度を柔軟に判断するよう規定の見直しが発表されました。今後はより幅広い企業で専門学校生の採用が可能になると予測されます。
雇用理由書の内容も重要
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請を成功させるためには、雇用理由書の内容が重要となります。
雇用理由書とは、雇用企業が申請人(申請人)を採用したい理由や業務の詳細などを記載した補足説明の書類で、在留資格の各種申請時に提出します。提出は必須ではありませんが、雇用理由書があることで審査がスムーズに進む可能性が高くなるのです。
雇用理由書には、以下の項目を記入しましょう。
- 申請(外国人)の情報
- 会社の規模
- 申請人(外国人)の経歴
- 申請人(外国人)の配属先
- 業務内容
- 外国人である申請人を採用すべき理由
あとがきとして、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の許可を強く希望する旨を記載するとより効果的です。決まったフォーマットはないので、自社で作成します。
なお、最後に会社名や代表名を記載し、捺印も忘れないようにしてください。
職種別「技術・人文知識・国際業務」申請のポイント
ここでは、「ホテル」「飲食店」「コンビニ」の勤務で、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を申請するポイントを解説します。
ホテル勤務での「技術・人文知識・国際業務」申請
WeXpats Agentではホテルの採用担当者様から「技人国での採用は可能か」とお尋ねいただくことがしばしばあります。
宿泊業で「技術・人文知識・国際業務」として外国人を雇用する場合、「フロント業務」「事務・営業業務」「支配人・マネジメント業務」での申請が可能です。
フロントで採用する場合、通訳のようなグローバルな業務が前提となるため、ホテルの利用者に外国人宿泊客が全くいない場合や、英語を話せない外国人を雇用する場合は、許可されないケースがあります。
当然ですが、支配人やマネジメントに従事させる場合は、日本人と同等以上の報酬を支払わなければ許可されないため、気を付けましょう。
【ホテル業務の許可事例】
- 学歴:日本の大学を卒業・外国語学専攻
- 業務内容:通訳・翻訳・外国語指導(観光客が多く利用する日本のホテルとの契約を締結。月額約20万円の報酬を受けて、集客拡大のための通訳・翻訳業務や従業員に対する外国語指導の業務などに従事する。)
飲食店勤務での「技術・人文知識・国際業務」申請
飲食店の主な業務内容のうち、キッチンやホールでの業務は単純労働とみなされ、不認可になるケースがほとんどです。ただし、「店舗管理・マネジメント業務」であれば認可される可能性があります。
以前は「店長候補」という名目で店舗への配属が認められる事例が多くありましたが、近年は厳しく審査される傾向があるため気を付けましょう。特に「一店舗の店長」としての雇用は難しくなってきています。
外食企業で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請する場合は、複数の店舗を統括するエリアマネージャーや本社の企画部など、よりハイレベルなキャリアを見据えた採用であることをアピールしてください。ただし、肩書は立派でも日本語スキルが足りずに不許可となったケースもあるので、あくまで実態に即した内容を記載するようにしましょう。
小さな店舗内で、管理業務のために外国人労働者を雇う必要性が感じられない場合や単純労働が疑われるケースでは、不許可になる可能性が高いといえます。具体的な基準として「店舗内に個人のワークデスクがあるかどうか」を見られる場合が多いので、事務作業用の机は確実に用意してください。
【飲食店業務の許可事例】
- 学歴:日本の専門学校を卒業(日本語能力検定N1合格)
- 日本企業で就労経験あり
- 業務内容:外国人客への接客マニュアルや外国語のメニュー表の作成(本社の管理センターに所属。外国人客に接客する際のマニュアルを作成し、従業員に指導を行う。日本語のメニューを外国語に翻訳。メニューのデザイン、Webサイト更新やパンフレット作製を行う。)
コンビニ勤務での「技術・人文知識・国際業務」申請
店長候補の採用であれば、コンビニ勤務でも「技術・人文知識・国際業務」が許可された事例はあります。
ただし、近年は審査が厳しくなっており、店長であっても実際は単純労働を行う時間が多いことから「一店舗の店長」としての雇用は難しくなってきています。
あくまで店舗勤務は将来を見据えた実地研修であり、複数の店舗を統括するエリアマネージャーや本社の企画部など、よりハイレベルなキャリアを見据えた採用であるとアピールできれば認可される可能性はあります。
【小売店(コンビニ)業務の許可事例】
- 学歴:日本の大学を卒業 経営学専攻(日本語能力試験N1合格)
- 業務内容:在庫管理と発注業務(在庫管理と発注業務を主とした事務職に従事。本店に所属し、個人の業務用デスクを持っている。勤務中は複数店舗を巡回し、それぞれの店舗ごとの状況を確認する。)
「自社の業務内容で申請が許可されるか不安」「外国人採用に必要な手続きがわからない」という企業の採用担当者の方は、「WeXpats Agent」の無料相談をご活用ください。経験豊富な担当者が丁寧にご説明いたします。
関連記事:「【企業向け】在留資格取り消しの事由や流れ~詳しい事例まで解説」
「技術・人文知識・国際業務」が不許可になる事例
以下では「技術・人文知識・国際業務」の申請が通らなかった不許可事例を紹介します。
学歴と業務内容に関連性がない
前述したように、専門的な知識が必要な業務の範疇であれば、大学の専攻と業務内容の関連性はそこまで厳しく確認されません。しかし、最終学歴が専門学校卒業の外国人を採用する場合は、専攻と業務内容の明確な合致が必要です。
【不許可事例】
専門学校で福祉について学んだ外国人が、通訳業務に従事する業務で申請。履修内容と業務内容の関連性が認められず不許可となった。
業務内容に専門性が認められない
在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、単純労働は認められていません。荷物の運搬や品出し、客室の清掃業務は、専門的知識や技術を必要としないと判断され、不許可となります。
【不許可事例】
専門学校で観光ビジネスを学び、ホテルでの勤務が決まった。しかし、主な業務内容は、宿泊客の荷物の運搬や客室の清掃業務だった。そのため、業務内容に専門性が認められず不許可となった。
日本人よりも報酬を低く設定
日本人と同じ業務内容の場合、外国人の報酬は日本人と同等かそれ以上に設定する必要があります。外国人であることを理由に給与を安く設定するのは禁じられており、申請しても不許可となるため気を付けましょう。
【不許可事例】
大学で情報学を専攻し、卒業後に月給20万円でシステムエンジニアとして採用が決まった。しかし、新卒のシステムエンジニアの報酬は月額22万円であるため、日本人よりも低く設定されているとして不許可となった。
外国人を雇用する必要性がない
外国人を雇用する必要が感じられない場合も、不許可になるケースがあります。なかでも、小さな規模で従業員が少ない会社などは、わざわざ「技術・人文知識・国際業務」で外国人を雇用する必要があるのかを疑われるでしょう。
外国人でなくても日本人従業員がカバーできる業務内容も、同様に不許可となるケースがあります。
【不許可事例】
大学で日本語学を専攻したベトナム国籍の者が、ホテルで通訳者として従事することが決まった。しかし、ホテルの利用者のほとんどが英語または中国語を利用するため、申請人の母語(ベトナム語)と業務で使用する言語が一致しておらず、不許可とされた。
外国人の在留中の素行が悪かった
外国人本人の過去の素行についても、「技術・人文知識・国際業務」審査の対象となります。大学や専門学校の出席率や成績、資格外活動許可を得た後ルールを守って働いていたかなども、許可を得るための大事なポイントです。
【不許可事例】
日本の外国語大学を卒業後、民間企業に語学教師として採用された。しかし、大学在学中に資格外活動許可の範囲を大きく超えて、長時間アルバイトしていたことが明らかとなった。そのため、在留中の素行が良くないと判断され、不許可となった。
「技術・人文知識・国際業務」が不許可になったら?
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得申請が不許可になった場合、まずは原因を把握することから始めましょう。
もし、学歴や業務の関連性が問題となっていた場合は、残念ながら同じ職種で再申請をしても不許可の可能性が高くなります。この場合は、外国人の採用を取り消すか、別の業務での採用を検討するなどの対応をしなければなりません。
しかし、書類の不備や雇用理由書での説明不足が原因の場合は、問題点を修正すれば再申請が許可される場合もあるのです。
審査に通らなかった際に届く不許可通知書には、詳しい理由は書いていません。地方出入国在留管理局に出向くと、面談で入国審査官からおおよその理由を教えてもらえます。
なお、再申請では最初の申請よりもより慎重に審査が行われるのが一般的です。再度不許可になるリスクを防ぐために、早めに専門家に申請を依頼することをおすすめします。
「技術・人文知識・国際業務」に当てはまる人材の採用方法
ここでは、新卒採用や中途採用、それぞれのケースに相応しい募集方法を解説します。
海外から呼び寄せる
海外で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する業務を行う外国人を、日本に招へいして雇用する方法があります。すでに日本に在留している外国人を雇用するよりも、手続きに手間がかかりますが、その分海外で実務経験や専門的な知識を身につけてきた人材を獲得できる可能性が高いでしょう。
海外から外国人を招へいする場合は、日本での仕事を探している人が利用する求人Webサイトを通して募集する方法があります。また、専門のエージェントを利用すると、在留資格適合性なども含め、自社にマッチした外国人の紹介を受けられるでしょう。
外国人留学生を採用する
日本の教育機関を卒業した外国人留学生を採用する方法もあります。独立行政法人日本学生支援機構の「令和5年度私費外国人留学生生活実態調査概要」によると、私費で日本に留学している外国人のうち、54.4%が日本での就職を希望していました。
しかし、実際は外国人留学生が応募できる求人が少ないのが現状です。そのため、外国人留学生が応募しやすい環境を整えれば、優秀な将来性のある人材を採用できる可能性が高まります。
留学生を雇用したい場合は、大学のキャリアセンターに求人を出したり専門学校にアプローチしたりするのがおすすめです。学校とのパイプ作りを行う手間はありますが、求人が目に止まりやすく応募を効率的に集められます。
中途採用で募集する
すでに日本で働いている外国人を中途採用で募集する方法もあります。
「技術・人文知識・国際業務」や身分に基づく在留資格を持って働いている外国人を採用できれば新たに申請する必要がないため、手続きにかけるリソースを減らせるでしょう。
また、日本のビジネスマナーや社会人としてのふるまいもある程度身についているため、入社後のミスマッチを起こしにくいというメリットもあります。
転職を希望する外国人は、日本の求人Webサイトを確認しているケースも多いので、幅広い日本の求人Webサイトから募集をかけましょう。
参照元:独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)「令和5年度私費外国人留学生生活実態調査概要」
「技術・人文知識・国際業務」の採用における注意点
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人を雇用する際は、採用上の注意を把握しておく必要があります。適正な雇用管理を行うためにも、以下の内容を覚えておきましょう。
「特定技能」を申請すべきケースもある
業務内容によっては、在留資格「技術・人文知識・国際業務」よりも、「特定技能」が相応しいケースもあります。
前述したとおり、在留資格「技術・人文知識・国際業務」では単純労働に分類される業務はできません。一方、「特定技能」は人手不足の業界のために創設された在留資格であるため、単純労働を含めた幅広い業務が可能です。
政府が人手不足と認めた業界(特定産業分野)でしか受け入れられないという注意点があるものの、日常会話レベルの日本語を測る試験と技能試験に合格すれば、在留資格を取得できます。
学歴や実務経験は問われないため、採用の間口も一気に広がるでしょう。専門的な業務よりは、単純作業を行える人材を求めている企業は、採用を検討してみてください。
特定技能については「【2024年6月最新】特定技能とは?制度や採用方法をわかりやすく解説」で詳しくまとめています。
申請から審査終了までは時間がかかる
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の審査には時間を要するので、入社時期に間に合うように余裕を持って申請しましょう。
年明けからは新年度に向けた各種申請で地方出入国在留管理局が混み合い、審査に時間がかかります。特に近年(コロナ禍明け)は申請が集中し、さらに時間がかかっているようです。
出入国在留管理庁の発表によると、2025年1月許可分の「技術・人文知識・国際業務」の審査処理時間は以下のとおりでした。
|
申請の種類 |
在留審査処理期間 |
|
在留資格認定証明書交付 |
60.9日 |
|
在留期間更新 |
32.9日(告知までの日数) |
|
在留資格変更 |
43日(告知までの日数) |
参照元:出入国在留管理庁「在留審査処理期間」
時期によってはさらに時間がかかることが予想されます。4月入社の場合、前年の12月1日ごろから申請できるので、解禁されたらすぐに申請できるよう準備を進めておきましょう。
副業やアルバイトは資格外活動許可を取得する
昨今では、本業とは別に仕事を複数掛け持ちして収入を増やす副業が一般化してきました。しかし、外国人が副業を始めるには資格外活動許可が必要となる可能性があります。
副業やアルバイトが「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で認められている活動であれば問題ありません。しかし、異なる場合は資格外活動許可を得ないと不法就労になります。雇用契約を結ぶ際には、副業に関する情報を共有しておきましょう。
異動で業務内容が変わる際は実務経験との関連性が重要
社内異動の可能性がある企業が外国人を雇用する際は、業務内容と在留資格で行える活動が一致しているかに注意を払う必要があります。
移動先の部署の業務内容が在留資格「技術・人文知識・国際業務」の範囲と一致しない場合、外国人従業員の就労が認められません。
「技術・人文知識・国際業務」の資格の中での変更は状況によって異なるため、地方出入国在留管理局に確認しましょう。
「技術・人文知識・国際業務」の更新時期を把握する
外国人を採用する際は、在留期間や更新時期がいつなのか把握しておきましょう。在留期限を過ぎたまま日本に在留する外国人は不法滞在者になり、そのまま雇用し続けた企業は「不法就労助長罪」で罰せられます。罰則内容は3年以下の懲役または300万円以下の罰金またはその両方と非常に重いものです。
「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は、3ヶ月・1年・3年・5年のいずれかが許可されています。初めて申請した際は1年更新となる場合が多いため、管理を徹底して外国人と更新申請の時期についてすり合わせを行いましょう。
参照元:出入国在留管理庁「在留審査処理期間」
まとめ
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、システムエンジニアや企画、翻訳業務などの専門的な知識や技術を要する職種で働く外国人が取得する在留資格です。取得には学歴や実務経歴などの要件があるので、採用したい外国人がチェック項目をクリアしているか確認しましょう。
外国人特化人材紹介サービス「WeXpats Agent」は幅広い職種・国籍・日本語レベルの人材にご登録いただいています。「技術・人文知識・国際業務」での採用をお考えの方はぜひご相談ください。

サービスを運営する中でよく伺うお悩みや質問に対して、真摯に向き合いながらも、分かりやすく、すぐに役立つコンテンツ発信を目指しています。






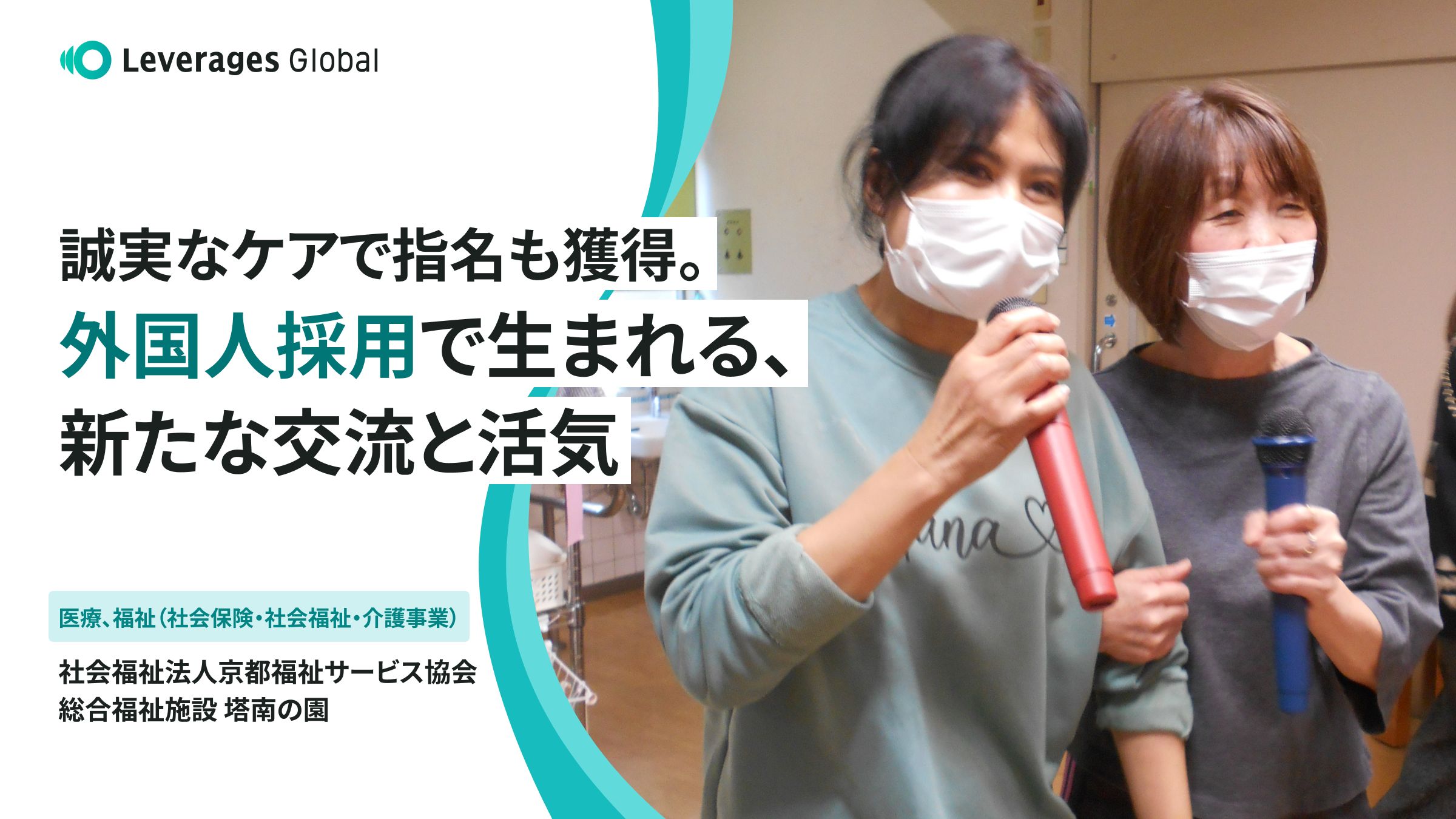
.png)





