
執筆: Leverages Global編集部 (ライター)
インドネシア人女性と一緒に働く中で、価値観や考え方の違いに戸惑った経験はありませんか?また、これから採用することを検討していて、特徴を知っておきたい企業担当者の方もいるでしょう。
インドネシアは多民族国家であり、宗教や文化、時間感覚など、日本とは異なる習慣を持っています。特にインドネシア人女性は家族や宗教を大切にしながら、明るくフレンドリーに周囲と接する人が多いのが特徴です。 この記事では、インドネシア人女性の特徴や仕事観、円滑に働くためのポイントを解説します。価値観の違いを理解し、信頼関係を築くための参考にしてください。
※本稿は「人種」や「国籍」といった特定の属性に対するイメージを単純化する意図はありません。本稿の内容は、あくまでインドネシアの文化や社会通念を紹介するものであり、個々人の性格は多種多様であるという点を踏まえてご覧ください。
外国人採用ならLeverages Global
外国人採用をもっと安心で簡単に、
はじめてみませんか?
支援実績多数!レバレジーズグローバルが支持される理由は、
以下サービス概要資料からご確認ください。
インドネシア人女性の性格と特徴
インドネシア人女性と一緒に働くうえで、どのような価値観や考え方を持っているのかを知ることはとても大切です。インドネシアには、多民族国家ならではの協調性や思いやりを重んじる文化があります。普段の生活の中で育まれてきた考え方や行動は、仕事にも表れることがあるでしょう。
ここでは、インドネシア人女性が持つといわれる特徴や考え方を紹介します。相手を理解するヒントとして、日々のコミュニケーションやサポートに役立ててください。
明るくフレンドリー
インドネシア人女性の多くは陽気で明るく、フレンドリーに人と接します。
コミュニケーションを取るときも、堅苦しい雰囲気はあまり感じられません。人と関わることに抵抗が少なく、初対面の相手とも自然に話せる人が多いのです。そのため、インドネシア人女性特有の柔らかな雰囲気が、職場全体を和やかにすることもあるでしょう。
明るく接するインドネシア人女性の姿勢は、コミュニケーションを円滑にする大きな魅力といえます。
ホスピタリティがある
インドネシア人女性は優しい人が多く、周囲の人に対して思いやりの心で接します。家族や友人に対してはもちろん、街中で困っている人を見かけたときにも、親切に声をかける人が少なくありません。
実際、厚生労働省の「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)」によると、医療・福祉に関連する職に就いている人の割合は、外国人全体の構成比が5.1%なのに対し、インドネシアは11.5%と高めです。直接的な関係があるかの判断は難しいですが、インドネシアにはホスピタリティが高い人が多いといえるでしょう。
助け合いの精神が根付いている
インドネシアには、「Gotong Royong(ゴトング ロヨング)」という言葉があります。これは、互いに助け合い、協力することを意味する言葉です。日常生活の中でも、この考え方は大切にされています。
インドネシアでは、困っている人がいればできる範囲で手を差し伸べることが自然です。助け合いの精神は、人との関わりをスムーズにするうえで欠かせない要素といえます。
家族を大事にする
インドネシア人女性は、家族を思いやる気持ちが強い傾向にあります。
インドネシア人にとって、家族は生活の中心です。親や祖父母、兄弟姉妹との絆を大切にしており、家族と過ごす時間が欠かせません。なかには、親戚と一緒に暮らしている人もいるほどです。
日本での就業は、「家族のため」という人も多くいます。
宗教を大切にしている
インドネシア人は男性・女性ともに、宗教を大切にしています。
なかでも、インドネシア人の87%がイスラム教を信仰するムスリムです。礼拝やラマダン、ハラール食など、日常の中で宗教的習慣を大切にしています。また、女性のムスリムは頭や体を覆うヒジャブを着用するのが一般的です。
職場では、信仰への理解と配慮を示すことが大切です。互いに尊重し合うことで、良好な関係を築けるでしょう。
楽観的で寛容
インドネシア人は男性・女性ともに、物事を前向きに考えるのが特徴です。
インドネシア人が日常的によく使う言葉に、「Tidak apa apa(ティダ・アパアパ)」があります。この言葉の意味は、「大丈夫」「気にしない」「なんとかなる」です。インドネシア人の楽観的で寛容な性格を表している言葉といえるでしょう。
実際、インドネシア人は予想外の出来事にも落ち着いて対応することが多く、他人のミスに対しても寛容です。
インドネシア人は男性・女性ともに、自分のリズムを大切にしながら生活している人が多い傾向にあります。焦って行動するよりも、落ち着いて確実に進めることを重視するのです。そのため、仕事において丁寧さが求められる場面では力を発揮するでしょう。
一方で、時間に対する意識が低く、日本人とは感覚が異なります。そのため、価値観の違いを理解したうえで、時間を守る大切さを伝えることが重要です。詳しくは、「時間厳守の重要性を伝える」をご確認ください。
参照元: 厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)」 外務省「インドネシア共和国」
関連記事:「外国人労働者を受け入れるメリット・デメリット|雇用の流れも解説」
インドネシア人女性の仕事観
インドネシア人女性は家族を大切にする思いが強く、その気持ちが仕事選びや働き方にも影響しています。また、仕事と私生活の区切り方や転職に対する捉え方も日本と違う部分があるでしょう。こうした背景を理解することは、円滑なコミュニケーションや定着支援を行ううえで欠かせません。
ここでは、インドネシア人女性の仕事観を紹介します。日々のマネジメントや指導の参考にしてください。
家族を支えるために働いている
インドネシアでは、家族を支えるために働くという考えが一般的です。女性も例外ではなく、親や兄弟姉妹、子どもたちのために働く人が多い傾向にあります。仕事を選ぶ際は、給料だけでなく家族との時間が取れるかを重視するのが特徴です。
日本で働くインドネシア人女性も、「家族に仕送りをするため」という人は少なくありません。特に、「特定技能」や「技能実習」の在留資格で来日している人は、その傾向がより強いといえるでしょう。
仕事とプライベートを分ける意識があまり強くない
インドネシアでは、仕事と私生活をきっちりと分ける考え方があまり浸透していません。仕事中におしゃべりをしたり、スマートフォンを操作したりするのは一般的で、なかには私用の買い物に行く人もいます。
そのため、日本で働き始めたばかりのインドネシア人に対して、「サボっている」や「非常識」と感じることもあるでしょう。ただし、多くの場合、本人にやる気がないわけではありません。インドネシアで培ってきた仕事への考え方や職場の雰囲気が、そのような行動につながっている場合が多いのです。
そのため、こういった背景を理解したうえで、日本の職場で求められる振る舞いやマナーを丁寧に伝えることが重要です。
転職が珍しいことではない
インドネシア人にとって、転職は決して珍しいことではありません。終身雇用の考えが根付いている日本に比べ、キャリアアップや収入向上のために転職を選ぶ人が多い傾向にあります。また、生活環境の変化や家庭の事情によって、職場を変えることも当たり前です。
採用する側としては、転職回数だけで判断するのではなく、その背景や理由を理解することが重要といえます。さらに、採用後は転職を防ぐために、居心地の良い職場環境やモチベーションを維持できるキャリアパスを整えることが大切です。
インドネシア人女性と円滑に働くためのポイント
インドネシア人女性と一緒に働くうえでは、文化や価値観の違いを理解することが欠かせません。
インドネシアと日本には、宗教や時間に対する感覚、コミュニケーションの取り方といった異なる点が多くあります。これらを理解し配慮する姿勢を持つことで、相手に安心感を与えられ、信頼関係の構築につながるでしょう。
ここでは、インドネシア人女性とより良い関係を築き、円滑に働くためのポイントを紹介します。
文化や価値観に配慮する
インドネシアは、多様な文化や価値観が混在している多民族国家です。日本とは、考え方や習慣において異なる点が多くあります。その一つが宗教です。
インドネシア人の多くはイスラム教徒(ムスリム)であり、日々の生活や働き方に宗教の教えが根付いています。具体的には、1日に5回お祈りを行うほか、約1ヶ月間日の出から日の入りまで飲食を断つ断食があります。また、戒律で豚肉やアルコールを口にしたり触れたりすることができません。さらに、女性の多くは頭や体を覆うヒジャブを着用しています。
このように、イスラム教では守るべき戒律がいくつもあるのです。とはいえ、戒律をどこまで守るかは人によってさまざま。そのため、一人ひとりの考え方を尊重しながら対応することが大切です。
たとえば、礼拝についてはお祈りができるスペースを用意すると良いでしょう。ヒジャブの着用についても、業務に支障がない範囲であればOKにすることで、安心して働いてもらえます。
イスラム教徒としての生活習慣を理解し、職場全体で協力することで、インドネシア人女性にとって働きやすい環境を整えられます。宗教や文化への理解は、信頼関係を築くうえで欠かせないポイントです。
インドネシアには「ゴム時間(Jam Karet)」という言葉があり、時間に対して柔軟に考える文化があります。ゴム時間とは、インドネシア人にとって時間はゴムのように伸び縮みするものという意味です。「おおらかでマイペ-ス」の項目でも述べたとおり、約束の時間に少し遅れても問題ないと捉えることが多く、日本のように厳密に時間を守る感覚は一般的ではありません。そのため、日本の職場で働き始めたばかりのインドネシア人女性が、遅刻や集合時間ギリギリの行動をしてしまうこともあります。
しかし、本人に時間を守る意思がないわけではなく、これまでの文化や習慣がそうさせている場合がほとんどです。だからこそ、業務において時間厳守がどれほど重要か、理由も含めて丁寧に伝える必要があります。
具体的には、始業時間や終業時間、休憩時間、締切などを明確に共有し、都度フィードバックすることが大切です。時間への意識を育てることで、よりスムーズな業務遂行につながるでしょう。
人前で叱責しない
多くのインドネシア人は、人前で注意されることを屈辱的と感じます。公の場で叱られると、恥をかかされたと受け止めてしまうのです。また、本人だけでなく、周囲のインドネシア人から反感を買ってしまう可能性も……。結果的に信頼関係の悪化や仕事への意欲低下につながってしまう恐れがあるため、叱責をする際には注意が必要です。
指導が必要な場面では、まずは落ち着いて原因や改善策を整理しましょう。そして、人目のない場所で、「何がいけなかったのか」「今後、どのようにしたら良いか」を冷静に伝えます。
インドネシア人女性に限らず、人前で叱責されて良い気分になる人はいません。円滑に働くためにも、相手の気持ちや立場に配慮した対応を心がけましょう。
関連記事:「外国人スタッフの教育は何をすれば良い?成功させるためのポイントも解説」
日本で働くインドネシア人は増えている
厚生労働省の「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)」によると、2024年6月末時点で日本で働くインドネシア人は16万9539人です。外国人全体における割合を見ると、7.4%と少ないように感じるでしょう。しかし、対前年増加率は39.5%と、前年より4万8032人も増えています。これは、ミャンマーに次いで2番目に大きい数字です。
今後も、日本で働くインドネシア人はさらに増えていく可能性があります。介護や外食業、製造業など、さまざまな分野でインドネシア人女性と接する機会が増えるかもしれません。
そのため、インドネシア人女性の特徴や仕事観をあらかじめ知っておくことが重要です。相手への理解が深まれば、コミュニケーションが円滑になるだけでなく、仕事を進めるうえでも良い関係を築きやすくなるでしょう。
参照元:厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)」
関連記事「国内人口増加中!インドネシア人の特徴や仕事観【職場に必要な宗教の配慮】」
まとめ
インドネシア人女性は、明るくフレンドリーで思いやりがあり、助け合いの精神を大切にする人が多いです。家族や宗教を大切にする気持ちも強く、その価値観は仕事への向き合い方や日々の行動に表れます。一方で、時間感覚やコミュニケーションの取り方が日本と異なる場合があり、理解不足からすれ違いが生じることもあるでしょう。
今後、インドネシア人女性と一緒に働く機会はさらに増えていくと考えられます。そのため、特徴や価値観、仕事観を知っておくことが重要です。
ただし、インドネシア人女性といっても、一人ひとり考え方や仕事に対する向き合い方は異なります。国籍だけで判断せず、一個人として理解し、文化や習慣を尊重する姿勢を持つことが大切です。そうすることで信頼関係が深まり、より良い職場環境を築けるでしょう。
インドネシア人の採用をはじめ、外国人採用をご検討中の企業様はお気軽にご相談下さい。 Leverages Globalでは、他の国籍の方の傾向や直近の登録者の情報を踏まえた情報共有が可能です。

サービスを運営する中でよく伺うお悩みや質問に対して、真摯に向き合いながらも、分かりやすく、すぐに役立つコンテンツ発信を目指しています。


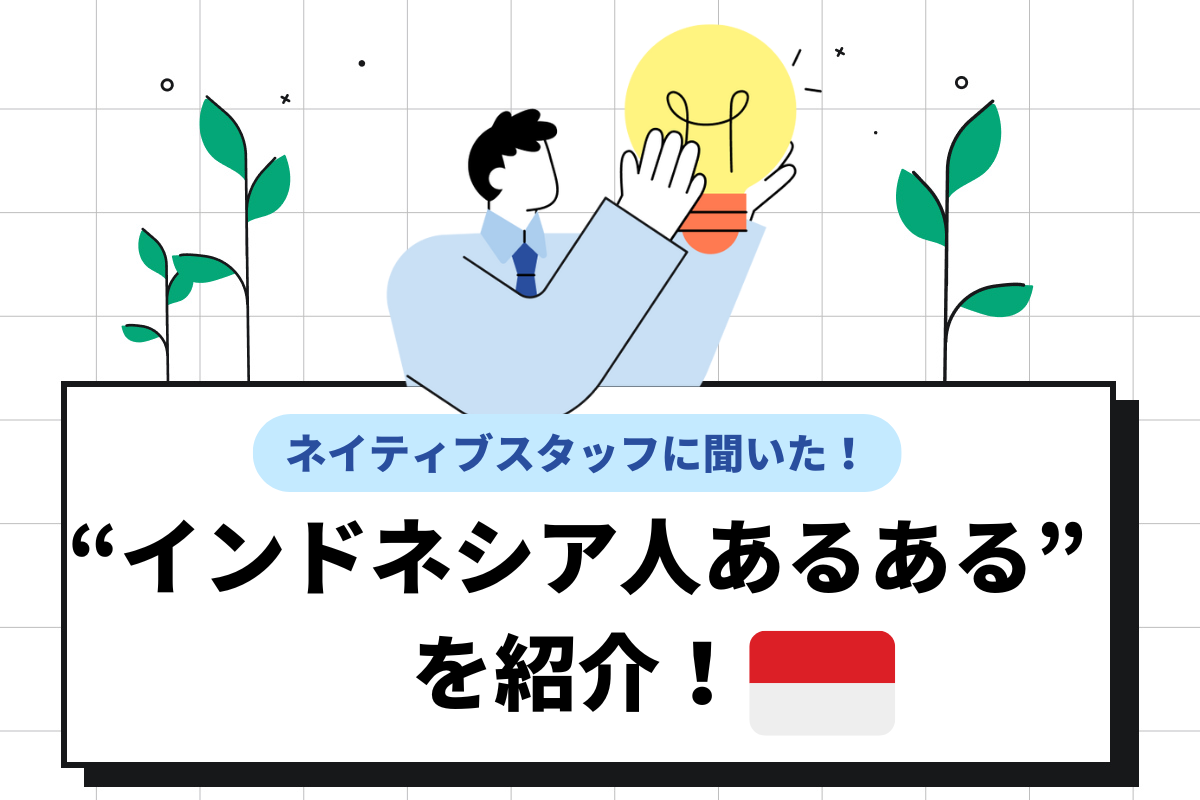


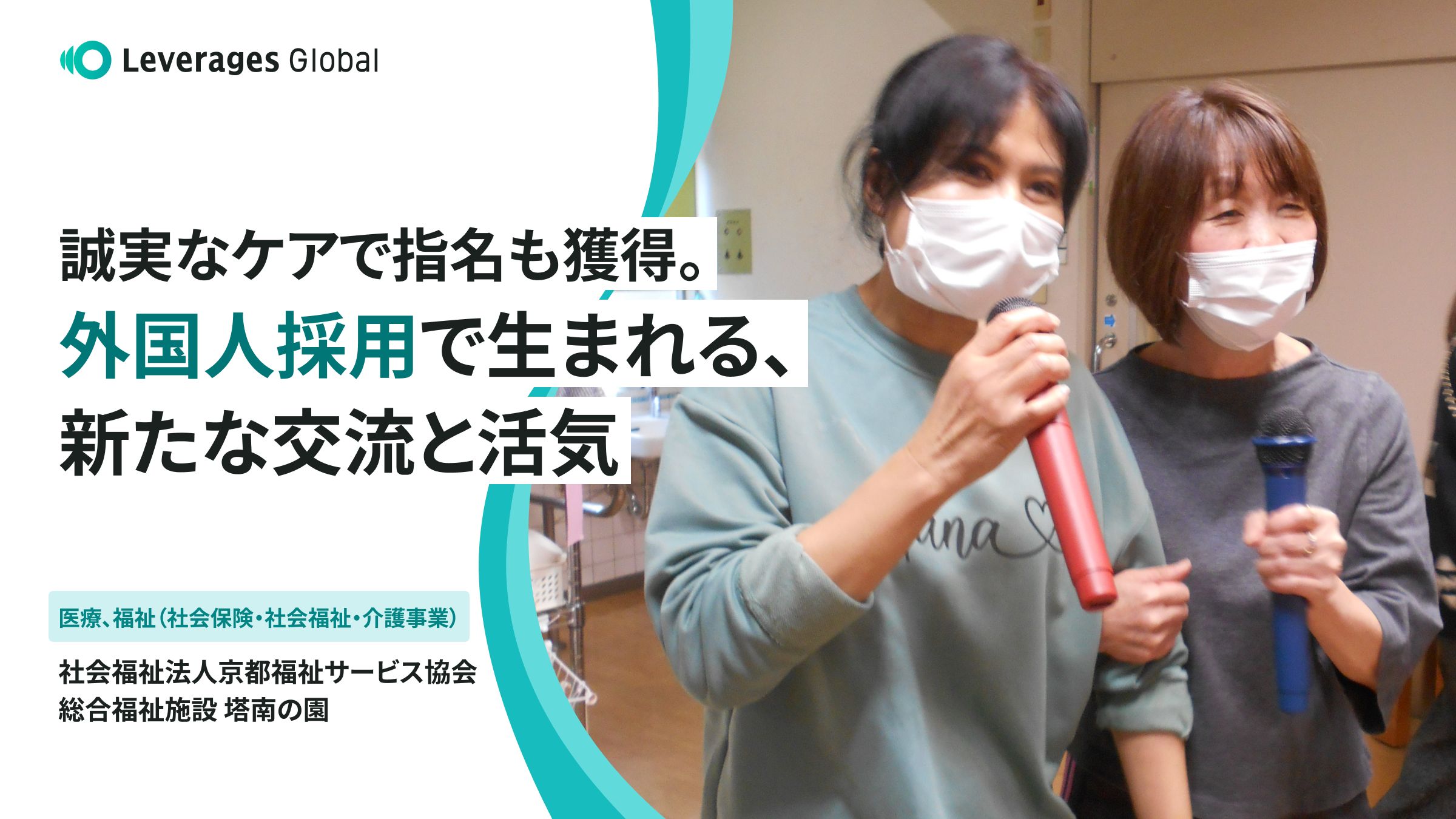
.png)





