
執筆: Leverages Global編集部 (ライター)
一緒に働く中で、ミャンマー人の穏やかで真面目な人柄に触れた方も多いでしょう。その価値観の根底にあるのは、国民の約9割が信仰する仏教の教えです。
この記事では、ミャンマーの宗教事情について解説。仏教の教えが育んだ国民性や職場で配慮すべきことも紹介します。相互理解を深め、より良い関係を築くためにぜひご活用ください。
※本稿は「人種」や「国籍」といった特定の属性に対するイメージを単純化する意図はありません。本稿の内容は、あくまでミャンマー人の文化や社会通念を紹介するものであり、個々人の性格や宗教観は多種多様であるという点を踏まえてご覧ください。
外国人採用ならLeverages Global
外国人採用をもっと安心で簡単に、
はじめてみませんか?
支援実績多数!レバレジーズグローバルが支持される理由は、
以下サービス概要資料からご確認ください。
ミャンマーにおける宗教割合
ミャンマーは、国民の生活と文化に宗教が深く根付いている国です。人々の価値観や行動様式を理解するためには、宗教的背景を知ることが欠かせません。信仰は、ミャンマー人のアイデンティティを形成する上で非常に重要な役割を担っています。
ここでは、ミャンマーの宗教に関する基本的な構成について解説します。
国民の約9割が仏教を信仰
ミャンマーは、国民のおよそ9割が仏教徒という世界でも有数の仏教国です。
街の至るところに黄金に輝くパゴダ(仏塔)や寺院が建立されており、人々の日常と仏教がいかに密接に結びついているかが伺えます。朝早くから僧侶へ食事を施して徳を積む人々の姿は、ミャンマーではごく当たり前の光景です。人生で一度は出家するという慣習を持つ男性も多くいます。
このように、仏教は単なる信仰の対象にとどまらず、生活規範や文化、人々の精神性の根幹を成す非常に大きな存在といえるでしょう。この仏教への深い信仰心が、後述するミャンマー人の穏やかさや勤勉さといった国民性を育んでいると考えられます。
キリスト教・イスラム教・ヒンドゥー教は少数
国民の大多数が仏教を信仰する一方で、ミャンマーには他の宗教を信仰する人々も暮らしています。キリスト教は主にカチン族やカレン族、チン族といった少数民族の間で信仰されており、その割合は全体の数パーセントです。
また、インドやバングラデシュと国境を接していることから、イスラム教徒やヒンドゥー教徒も少数ながら存在します。彼らは独自のコミュニティを形成し、それぞれの文化や信仰を守りながら生活を営んでいるのです。
外務省「ミャンマー基礎データ」
ミャンマーに根付く仏教の特徴
ミャンマーで信仰されている仏教は、日本の大乗仏教とは異なる特徴があります。
たとえば、人々が日々熱心に行う「徳を積む」という行為や出家などは、日本ではあまり馴染みがないかもしれません。また、古くから伝わる土着の信仰と仏教が融合し、独自の文化を形成している点も特徴です。
ここでは、ミャンマーに根付く仏教の特徴を紹介します。
上座部仏教
ミャンマーで広く信仰されているのは「上座部仏教」です。タイやカンボジア、スリランカなど東南アジアの国々で主流となっている仏教で、ブッダが説いた教えや戒律を厳格に守ることを重んじています。
日本の多くの宗派が属する「大乗仏教」がすべての人々の救済を目指すのに対し、上座部仏教は出家した僧侶が厳しい修行を通して、まず個人の悟り(解脱)に到達することを第一の目的としています。そのため、僧侶は社会的に非常に尊敬される存在です。在家信者は、その修行を支えるために食事の提供や寄付といった「タンブン(徳を積む行為)」を熱心に行います。
この行いが、来世の幸福につながると信じられているのです。
出家して個人の解脱を目指す
上座部仏教の最大の特徴は、出家して厳しい修行を通じて「解脱」を目指すことです。
解脱とは、輪廻転生の苦しみから解放されることを意味します。この目的を達成できるのは、厳しい戒律を守り、瞑想などの修行に専念する僧侶だけだと考えられています。
ミャンマーの男性は人生で一度は僧院に入り、短期間でも出家生活を体験する得度式を行うのが一般的です。これは、親への恩返しや成人になるための通過儀礼としての意味合いを持ちます。この経験を通じて、仏教の教えや規律を学び、一人前の社会人としての人格を形成していくのです。
厳しい戒律を厳格に守る
上座部仏教は、ブッダが定めた戒律を忠実に守ることを重要視しているのが特徴です。僧侶が守るべき戒律は227項目にもおよび、食事の時間や金銭の所有、殺生など、日常生活の細部にわたって厳しい決まりがあります。
たとえば、僧侶は正午以降に固形物を口にすることができません。また、異性との接触もNGです。在家信者も、日常生活において「五戒(殺生・盗み・邪淫・嘘・飲酒をしない)」を守ることが推奨されており、これが社会の道徳的な基盤となっています。
功徳を積むことが重要
ミャンマーの人々の生活において、功徳を積むことは非常に重要な意味を持ちます。
功徳とは、良い行いをすることで得られる幸福や良い報いのことです。功徳を積むことで、現世や来世がより良いものになると信じられています。
功徳を積む最も代表的な行為が、僧侶への食事の施しや寺院への寄付です。そのほかにも、困っている人を助ける、嘘をつかないといった日常のささいな善行も功徳となります。
生まれた曜日を重要視する
ミャンマーでは、自分が生まれた曜日が非常に重要な意味を持つと考えられています。これは仏教そのものの教えではありませんが、古くからの占星術や土着の信仰が仏教と融合して生まれた独自の文化です。
人々は自分の生まれた曜日を知っており、その曜日に対応した方角や動物、守護神が存在します。パゴダを訪れると、境内にはそれぞれの曜日を表す祭壇が設けられています。人々は自分の曜日の祭壇へ行き、守護仏に水をかけて熱心に祈りを捧げるのです。
また、生まれた曜日によって名前が決まります。たとえば、日曜日生まれなら「アウン」や「エー」、月曜日生まれなら「チョー」や「キン」などです。
仏教に関する祭日がある
ミャンマーの年中行事は、仏教と深く結びついています。年間を通じて多くの仏教関連の祭日があり、人々にとって大切な祝日となっているのです。
その中でも最大のお祭りが、4月中旬に行われる「ティンジャン(水かけ祭り)」です。ミャンマーの新年を祝うお祭りで、仏像を清める儀式に由来しています。人々は互いに水をかけ合って旧年の汚れを洗い流し、新年を迎えるのです。また、10月頃には「ダディンジュ」があり、家々やパゴダに明かりを灯してブッダを迎えます。
仏教に関する祭日は、多くの人が故郷に帰省し家族や親戚と過ごす大切な期間です。企業はこうした文化的な背景を理解し、ミャンマー人従業員の休暇取得希望に対して柔軟に対応することが望ましいでしょう。
宗教観が育んだミャンマー人の国民性
上座部仏教の教えはミャンマー人の道徳観や倫理観の基礎となっており、それが日々の行動や人との接し方に自然と表れています。
たとえば、「功徳を積む」という考え方は、他人への親切や思いやりを育みます。また、厳しい戒律を守る僧侶を尊敬する文化は、目上の人を敬う礼儀正しい態度につながるでしょう。もちろん、すべての人が同じ性格ではありませんし、個人差があることは大前提です。しかし、宗教的な価値観を知ることは、ミャンマー人従業員と良好な関係性を築く上で非常に役立つでしょう。
ここでは、仏教の教えがどのようにミャンマー人の国民性を育んできたのかを解説します。
目上の人を敬い礼儀を重んじる
ミャンマーでは年長者や社会的地位の高い人、僧侶といった目上の人を敬う文化が社会全体に深く根付いています。ミャンマー人は言葉遣いやお辞儀の仕方、物の受け渡し方など、日常のさまざまな場面で相手への敬意を示しているのです。
この文化は、日本の先輩・後輩といった関係性とも親和性が高いでしょう。そのため、ミャンマー人は日本の職場環境にも比較的スムーズに順応できることが多いです。上司や先輩の指示を素直に聞き入れ、謙虚な姿勢で仕事に取り組むでしょう。
ただし、敬意の念が強いあまり、自分の意見を主張することにためらいを感じる場合もあります。そのため、発言しやすい雰囲気作りをすることが大切です。
穏やかで他人に対して寛容
ミャンマー人の多くは、穏やかで争いを好まない性格を持っています。これは、仏教において怒りや憎しみといった感情を抑えることが善しとされるためです。人前で感情をあらわにすることは「みっともないこと」と捉えられる傾向にあります。そのため、他人との間に問題が生じた場合でも、感情的に対立するのではなく、穏便に解決しようと努めるでしょう。
また、「功徳を積む」という教えから、他人に対して親切で寛容な態度で接することが習慣となっています。困っている人がいれば、自然に手を差し伸べる優しさを持っているのです。
こうした性質は、職場のチームワークを重んじ、円滑な人間関係を築く上で大きな長所となります。周囲と協力しながら業務を進める環境で、その力を発揮してくれるはずです。
勤勉で真面目
ミャンマー人の勤勉さは、「功徳を積む」という価値観に支えられています。真面目に働くこと自体が、自分や家族の来世を良くするための善行であると捉えているのです。そのため、与えられた仕事には責任を持って取り組み、困難な作業でも投げ出さずにコツコツと努力を続けます。
また、学習意欲が高いのも特徴です。新しい知識やスキルを積極的に吸収しようと努力します。こういった勤勉な姿勢は日本企業が求める人材像とも合致する部分が多く、さまざまな業種で活躍が期待できるでしょう。
家族を大切にする
ミャンマー人にとって家族は心の支えであり、何よりも大切な存在です。ミャンマー人が日本で働く主な動機の一つとして、家族により良い暮らしをさせてあげたいという強い思いが挙げられます。この家族への愛情や責任感が、仕事に対する高いモチベーションにつながっているのです。
また、ミャンマーには人生の重要な決断をする際には必ず家族に相談し、その意見を尊重する文化があります。企業側はこうしたミャンマー人の強い家族愛を理解し、尊重することが重要です。家族の病気や冠婚葬祭などによる一時帰国の希望があった際には、可能な限り対応しましょう。
宗教的観点からミャンマー人に配慮すべきこと
ミャンマー人従業員に気持ちよく働いてもらうためには、宗教観や文化に配慮した職場環境を整えることが大切です。日本では当たり前とされていることでも、ミャンマー人にとっては受け入れがたいことがあります。
たとえば、食事に関する習慣や祈りの時間、宗教的な祝祭日への考え方などは事前に確認し、できる限りのサポート体制を築くことが望ましいでしょう。
こうした配慮は、単にトラブルを避けるためだけではありません。会社が自分たちの文化を尊重してくれていると感じることは、仕事へのモチベーション向上に直結します。相互理解の姿勢を示すことが、長期的な信頼関係を築く上で最も重要なことです。
関連記事:外国人との異文化コミュニケーションに必要なこと|心構えや失敗例も
日本で働くミャンマー人は増えている
近年、日本国内で就労するミャンマー人の数が著しく増加しています。
出入国在留管理庁のデータを見ると、2024年10月末時点で日本で働いているミャンマー人の数は11万4,618人でした。外国人労働者全体の5%とそう多くはありませんが、対前年増加率は60%です。2位のインドネシア(39.5%)、3位のスリランカ(33.7%)と比べると、その差は歴然です。
この背景には、日本の人手不足とより良い就労機会を求めて海外を目指すミャンマー人のニーズが合致していることが挙げられます。特に技能実習や特定技能といった在留資格で来日するケースが多く、介護・建設・農業・製造業といった幅広い分野で活躍しています。
ミャンマー人の真面目な働きぶりや日本人と親和性の高い国民性は、多くの受け入れ企業から高く評価されています。今後もこの傾向は続くと予測され、ミャンマー人材は日本社会にとってますます重要なパートナーとなっていくでしょう。
参照元:「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)」
関連記事:増加率1位!ミャンマー人の特徴や仕事観を紹介【必要な配慮とは】
まとめ
ミャンマーは、国民の約9割が敬虔な上座部仏教徒であり、その教えが人々の生活や価値観の隅々にまで深く浸透している国です。ミャンマー人の穏やかさや勤勉さ、目上の人を敬う心は、すべてこの信仰心に根差しているといえるでしょう。「功徳を積む」という考え方は、ミャンマー人の行動を理解する上で最も重要なキーワードです。
ミャンマー人と良好な関係を築くためには、こうした宗教的背景を理解し、尊重する姿勢が欠かせません。彼らの信仰に敬意を払うことで、安心して働ける環境を整えることができます。相互理解を深めることが、ミャンマー人の持つ素晴らしい能力を職場で最大限に引き出す鍵となるでしょう。

サービスを運営する中でよく伺うお悩みや質問に対して、真摯に向き合いながらも、分かりやすく、すぐに役立つコンテンツ発信を目指しています。


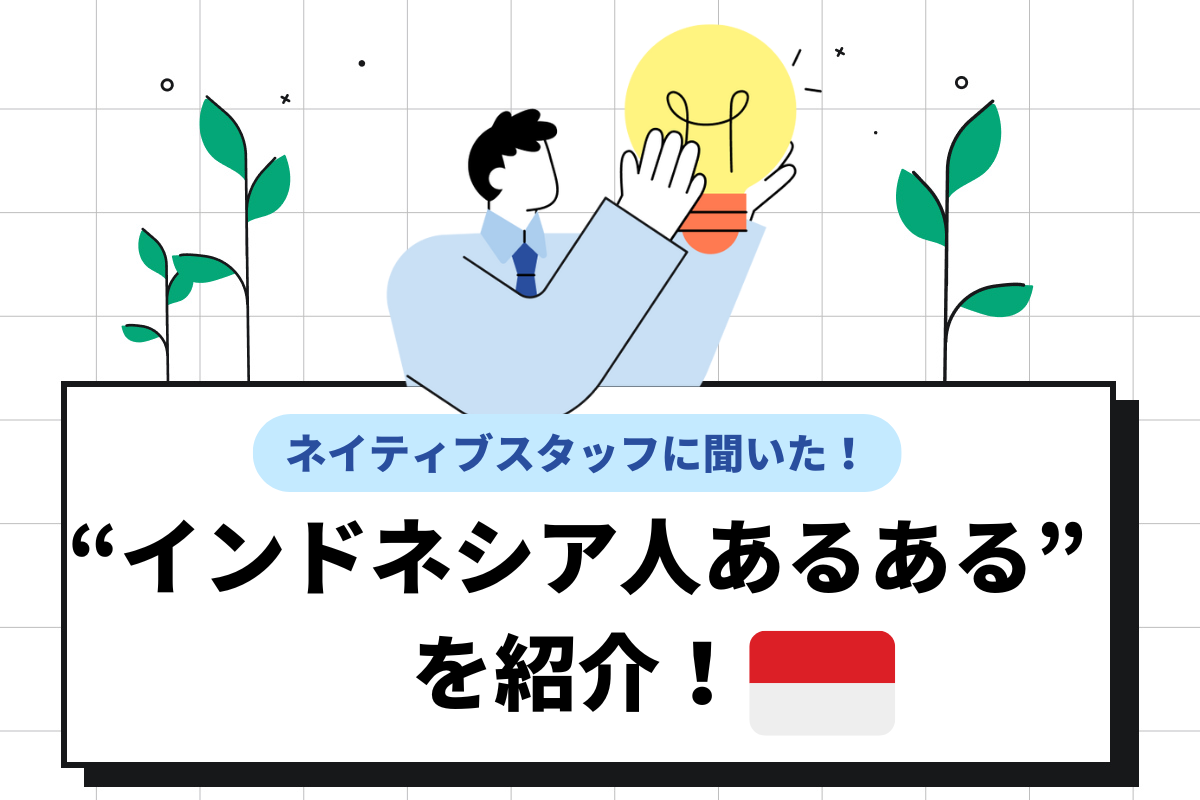


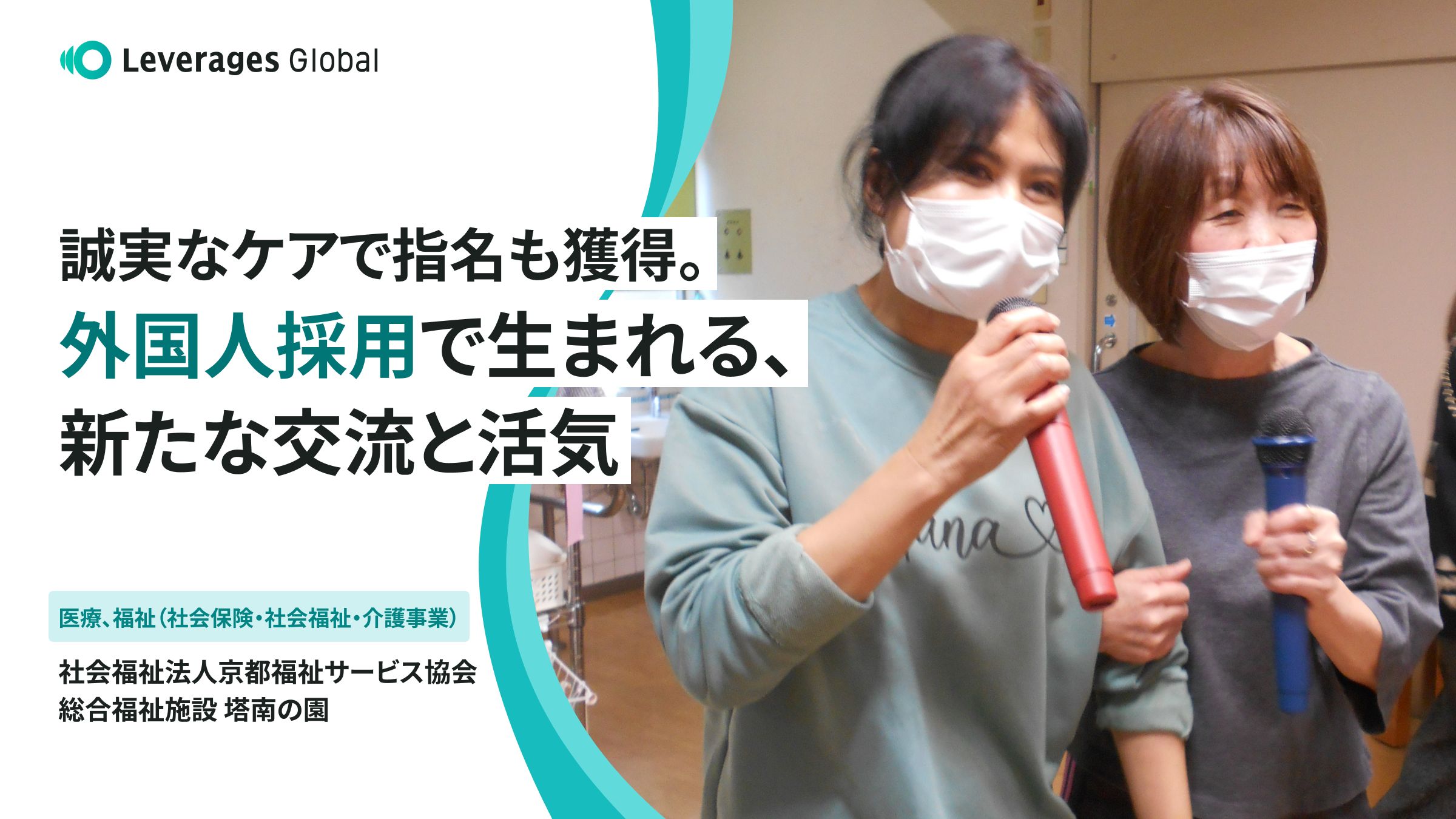
.png)




