
執筆: Leverages Global編集部 (ライター)
技能実習制度の代わりに導入される育成就労制度は、特定技能制度への移行が前提となっています。そのため、受け入れ分野が共通しているのが特徴です。これから外国人雇用を検討している企業の方は、どちらの制度が自社に合っているかよく検討してみましょう。
本記事では、育成就労制度と特定技能制度、それぞれの概要を解説します。どちらかの制度を使って外国人雇用を検討している企業は、ぜひ参考にしてください。
外国人採用ならLeverages Global
外国人採用をもっと安心で簡単に、
はじめてみませんか?
支援実績多数!レバレジーズグローバルが支持される理由は、
以下サービス概要資料からご確認ください。
育成就労制度と特定技能制度は関係ある?
2027年の6月までに施行される予定の育成就労制度は、特定技能制度への移行を前提とした制度です。
制度としては、育成就労制度を利用して日本に入国した外国人を、原則3年の間に特定技能1号と同じ水準の技能を有するところまで育成することを目指しています。そのため、育成就労制度の受け入れ対象分野は、特定技能制度の対象分野と連動する予定です。
育成就労制度と特定技能制度の最も大きな違いは制度の目的。特定技能制度は、人材不足の解消に繋がる即戦力となる外国人人材を確保するために創設されました。一方育成就労制度は、就労を通して外国人をいずれ企業の即戦力となるような人材に育成することに重きを置いています。
参照元:JITCO公益社団法人 国際人材協力機構「育成就労制度とは」
特定技能制度とは
ここでは、育成就労制度と密接に関係する特定技能制度の概要を解説します。今後さらに利用する外国人や企業が増加すると予想される制度なので、しっかり内容を把握しておきましょう。
人材不足解消のための制度
特定技能制度は、対策をしても人材不足の解消が困難だった産業分野(特定産業分野)において、一定の専門的な技能を有する外国人人材を雇用しやすくするための制度です。
本来、外国人が就労を目的に在留資格を取得する際は、専門的な学歴や実務経験が必要となります。しかし、在留資格「特定技能1号」に関しては主に以下の条件を満たせば取得可能です。
- 各分野の技能試験合格
- 日本語能力試験(JLPT)のN4以上の取得、もしくは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-basic)への合格
- 技能実習2号を良好に修了(技能実習の職種・作業と特定技能の業務に関連がある場合は試験免除)
このように、学歴や実務経験の制限はないため、比較的取得しやすい在留資格といえるでしょう。
特定技能制度を利用できる業界(分野)
特定技能制度の利用は、対策を講じても国内の人材だけでは人材不足解消に至らなかった業界である「特定産業分野」にのみ認められています。
特定産業分野に定められている業界は以下のとおりです。
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 自動車運送業
- 鉄道
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 木材産業
特定技能外国人は、在留資格「特定技能」のもと、上記の分野で一定の知識や経験を必要とする業務に従事できます。また、特別な技能を必要としない業務も条件付きで許可されているため、日本人と同等の仕事をある程度任せることが可能です。
在留資格の種類
在留資格「特定技能」には、1号と2号の2種類があります。1号を取得するのに必要なのは「相当程度の知識または経験を必要とする技能」です。2号を取得するためには「熟練した技能」が求められます。
特定技能制度で働く外国人は、まずは「特定技能1号」を取得し、「評価試験に合格」「管理・指導の実務経験(およそ2年以上)という条件を満たせば、「特定技能2号」に移行可能です。
特定技能1号と2号には、大まかに以下の違いがあります。
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
| 求められる技能 | 相当程度の知識又は経験が必要な技能 | 熟練した技能 |
| 在留期間 | 通算5年まで更新可能 | 更新の制限なし |
| 家族の帯同 | 不可 | 条件付きで可 |
| 永住権 | 申請不可 | 条件を付きで可 |
| 取得条件 | 日本語と技能試験に合格 | ・高度な技能試験に合格 ・一定の実務経験 |
| 支援計画 | 必要 | 不要 |
なお、介護分野は在留資格「介護」への移行が想定されるため、2号の対象外になっています。また、2024年に追加された「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」も、2025年7月時点では2号対象外です。
登録支援機関について
はじめて特定技能制度を利用する際は、支援業務を登録支援機関に委託することになるでしょう。
特定技能外国人を雇用する企業には、支援業務の実施が義務付けられています。支援業務とは、特定技能外国人が日本で安定的かつ円滑に活動を行うために必要な、日常生活上・社会生活上のサポートのことです。
自社で支援を行うことも可能ですが、人員が必要となるため人手不足の場合は適切な実施が難しいでしょう。また、自社で支援を行うには過去2年以内に外国⼈労働者を雇ったり管理したりした実績が必要です。そのため、初めて外国人雇用をする企業は、基本的に支援業務を登録支援機関に委託します。
登録支援機関になるのは、行政書士や技能実習監理団体、人材紹介会社などです。人材紹介会社を利用して特定技能外国人を雇用する場合は、支援業務も行っていないか確認してみましょう。
Leverages Global(レバレジーズグローバル)も、人材紹介のみならず登録支援機関として貴社のサポートが可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。
参照元:出入国在留管理庁「受入れ機関の方」
育成就労制度とは
ここでは、育成就労制度の概要を解説します。なお、育成就労制度はまだ始まっておらず、不確定な部分も多い制度です。2027年の施行までに変更点がある可能性もあるので、参考までにご覧ください。
技能実習に代わる制度
育成就労制度は、廃止が決定された技能実習制度に代わる制度として創設されました。
制度技能実習制度が廃止された背景には、制度が本来の「国際貢献」という目的から離れ、人手不足の企業の「人材確保」のために利用されてきたこと、また、技能実習生の人権侵害が問題視されてきたことが挙げられます。
育成就労制度は、人材育成と人材確保の両方を目的に運用される制度です。育成就労で在留する3年の期間で外国人に技能を修得させ、在留資格「特定技能1号」へ変更することを前提としています。
受け入れ対象分野は特定技能制度に合わせる見込み
育成就労制度で外国人を受け入れる分野(育成就労産業分野)は、特定技能制度の分野(特定技能分野)に合わせる見込みです。
育成就労制度からの移行がしやすくなるよう、特定制度の対象分野や対象業務も追加されています。たとえば、2024年には特定産業分野に「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4つが追加されました。
なお、技能実習の一部の職種・作業においては、育成就労制度の対象外になるものもあります。企業の人材採用の方向性に影響してくるので、最新情報をチェックしておきましょう。
外国人の支援や保護がより強化される内容になる
技能実習制度の在り方が人権保護の観点から問題視されたことを踏まえ、育成就労制度では外国人に対する支援や保護がより強化されます。
詳しい変更点は後述しますが、育成就労制度では受け入れ機関や監理支援機関の許可要件を厳格化する予定です。また、二国間取り決め(MOC)を作成した国からのみ外国人を受け入れ、悪質な送り出し機関の根絶を目指します。
技能実習制度から特定技能制度へ代わるタイミング
育成就労制度がスタートする日程は未定ですが、改正法が公布された2024年6月21日から3年以内に施行される見込みです。
施行日までに技能実習計画を認定し、3ヶ月以内に技能実習を開始した外国人は、育成就労制度が開始したあとも引き続き技能実習生を行うことができます。つまり、育成就労制度は開始して3年程度は、技能実習制度と併行して行われる予定です。
なお、育成就労制度の開始後は技能実習3号への移行は制限され、特定技能への移行が進められます。
参照元:出入国在留管理庁「育成就労制度・特定技能制度Q&A」
育成就労制度と技能実習制度の違い
ここまでは、育成就労制度と特定技能制度について説明してきました。ここでは、育成就労制度についての理解を深めるために、前身となる技能実習制度についても知っておきましょう。
育成就労制度と技能実習制度の主な違いは以下のとおりです。
| 育成就労制度 | 技能実習制度 | |
| 制度の目的 | ・人材育成 ・人材確保 | ・人材育成 ・国際貢献 |
| 転職 | 条件を満たせば可能 | 原則不可 |
| 対象職種 | 育成就労産業分野 | 移行対象職種 |
| 在留期間 | 原則3年 | 最長5年 |
| 関係機関 | 監理支援機関 | 監理団体 |
| 在留資格 | 育成就労 | ・技能実習1号 ・技能実習2号 ・技能実習3号 |
| 送り出し機関の利用 | MOC作成国のみ | MOC作成国以外も可能 |
以下で各項目についてさらに掘り下げて解説します。
制度の目的
先述したとおり、育成就労制度には技能実習制度にはなかった「人材確保」という目的が追加されました。
技能実習制度は、開発途上国などの外国人に日本で培われた技術や知識を教え、母国の経済発展に繋げるという国際貢献の意味合いの大きい制度です。育成就労制度では、国際貢献という目的が除外されたのが大きな違いといえるでしょう。
転職
育成就労制度では、技能実習制度ではやむを得ない場合を除き禁止されていた転職(転籍)が、一定の条件を満たせば認められます。以下の条件を満たせば自分の希望の転職も可能になる予定です。
- 同一業務区分内であること
- 同じ機関で1~2年働いていること(期間は分野ごとに決定)
- 技能検定試験基礎級等及び分野ごとに設定するA1~A2相当の日本語能力に係る試験へ合格していること
- 転籍先が育成就労を適正に実施する基準を満たしていること
転職が認められるようになった背景には、労働者として働く外国人が自分の意思で職場を変えられないのは、人権侵害に当たるのではという声があったためです。また、技能実習生の失踪が絶えないのは、転職が制限されていることが要因の一つだという意見が多かったのも影響しているでしょう。
対象職種
技能実習制度の対象職種は、91職種168作業(2025年8月時点)あります。一方、育成就労制度の対象職種(育成就労産業分野)は、先述したとおり特定技能制度の16分野に合わせる予定です。
在留期間
技能実習制度の在留期間は1号(1年)、2号(2年)、3号(2年)の最長5年間です。一方、育成就労制度の在留期間は原則3年と定められます。ただし、特定技能に移行するための試験に受からなかった場合など、理由があれば1年延長できる予定です。
関係機関
技能実習を実施する際は、監理団体の支援や指導を受けるのが一般的です。育成就労制度では、監理団体に代わる機関として監理支援機関が作られます。
監理支援機関はより要件を厳格化し、外部監査人設置の義務化や役職員の監理への関与制限などが定められる見込みです。
在留資格
技能実習制度のもと日本で実習を行う外国人には、在留資格「技能実習1号」が付与されます。移行試験を受けることで、2号・3号と移行が可能です。
育成就労制度のもと就労する外国人には、制度施行のタイミングで創設される在留資格「育成就労」が付与されます。
送り出し機関
送り出し機関とは、候補者となる外国人を集め、日本に送り出す現地機関です。育成就労制度でも、技能実習制度と同様に送り出し機関を利用して人材を雇用できます。ただし、悪質な送り出し機関の介入を防ぐため、育成就労制度では二国間協力覚書(MOC)を締結した国からのみ、人材を募集する予定です。
育成就労制度と特定技能制度のそれぞれのメリット
育成就労制度と特定技能制度、どちらで外国人を雇用したら良いのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。それぞれ特徴が異なるので、自社に合った制度を選ぶことが大切です。
ここでは、育成就労制度と特定技能制度それぞれのメリットを解説するので、外国人雇用を始める際の参考にしてください。
育成就労制度で外国人を雇用するメリット
育成就労制度で外国人を雇用すると、採用の間口が広く取れるというメリットがあります。
育成就労制度を利用する外国人の要件は、「日本語能力A1相当以上の試験に合格またはそれに相当する日本語講習の受講」です。日本語能力A1相当は日本語能力検定(JLPT)のN5に相当します。基本的な日本語がある程度理解できるレベルで、毎日1時間の勉強を3ヶ月継続すれば合格が可能で、難易度はそこまで高くありません。
技能の要件は設けられておらず、育成就労制度で働きながら覚えていくかたちになります。
分野ごとに日本語要件が設けられる可能性はありますが、現時点では求められている能力はそう高くないので、多くの外国人のなかから候補者を選定できるでしょう。
特定技能制度で外国人を雇用するメリット
特定技能制度で外国人を雇用するメリットは、即戦力となる人材を雇用できることです。
特定技能制度で働くには、技能試験および日本語試験に合格する必要があります。また、技能実習である程度経験を積んだ外国人が多いのも特徴です。
特定技能制度への移行が前提となっている育成就労制度がスタートすれば、より経験を積んだ人材を獲得しやすくしやすくなるでしょう。
人材不足の企業にとって、すぐに活躍してもらえる人材を雇用できることは大きなメリットです。
まとめ
育成就労制度は、人材確保と人材育成を目的に作られました。育成期間を経て特定技能制度へ移行すれば、長期的な雇用が可能です。
「育成する余裕がない」「即戦力が欲しい」という場合は、在留資格「特定技能」を持つ外国人を雇用するほうがスムーズといえます。
育成就労制度の施行までに徐々に情報が発表されるので、最新情報をチェックしておきましょう。

サービスを運営する中でよく伺うお悩みや質問に対して、真摯に向き合いながらも、分かりやすく、すぐに役立つコンテンツ発信を目指しています。




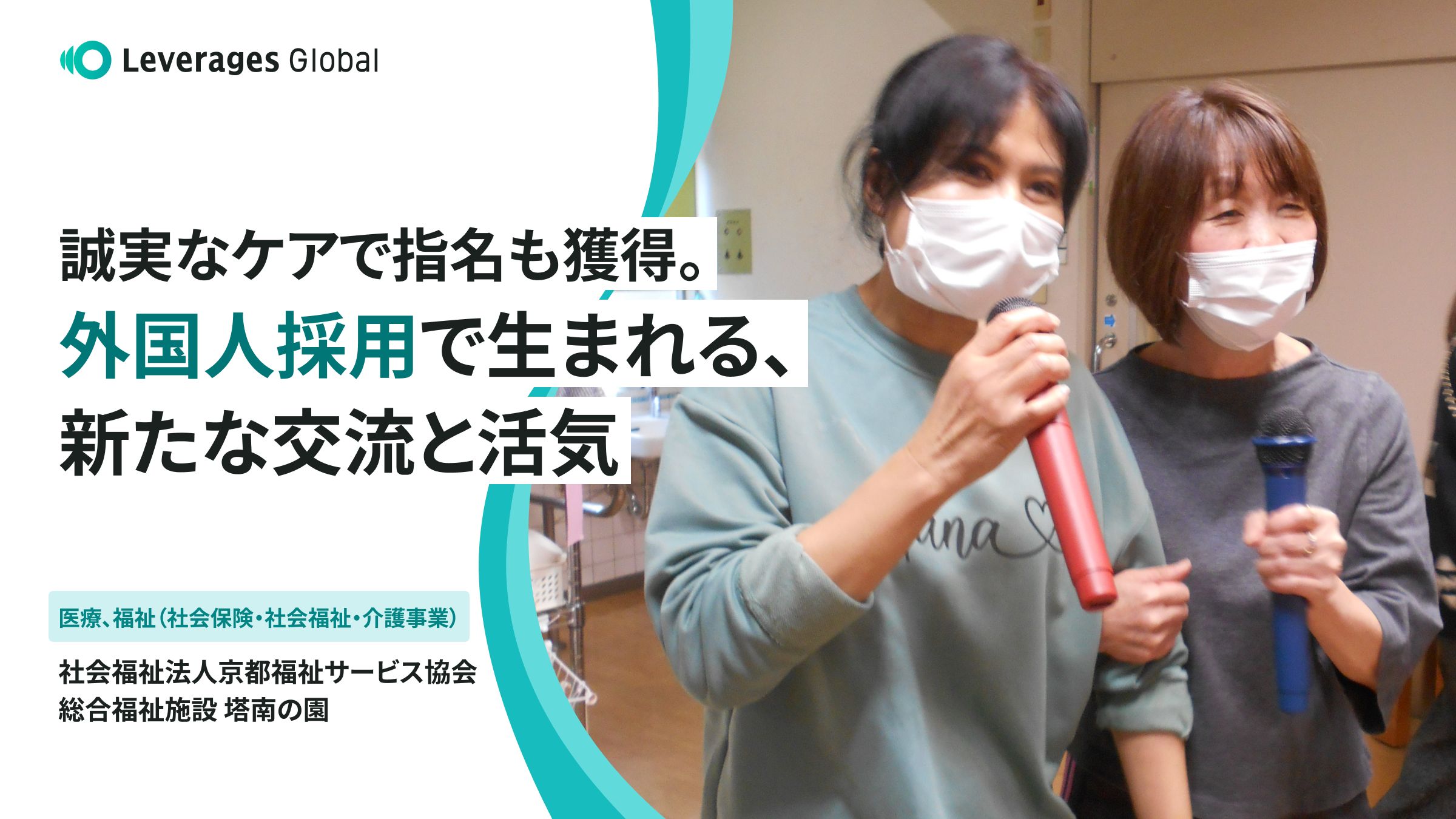
.png)





