
執筆: Leverages Global編集部 (ライター)
2024年6月14日の国会にて、技能実習制度の廃止とそれに代わる育成就労制度の新設が決まりました。いつから育成就労制度が本格的にスタートするのか、またいつから技能実習生を受け入れられなくなるのか、気になっている企業の方も多いでしょう。
この記事では、育成就労がいつから始まるのか、また、技能実習制度とどのような点が変わるのかを解説します。内容を参考にして、自社での外国人雇用に活かしましょう。
外国人採用ならLeverages Global 外国人採用をもっと安心で簡単に、 支援実績多数!レバレジーズグローバルが支持される理由は、
はじめてみませんか?
以下サービス概要資料からご確認ください。
育成就労制度はいつから始まる?基本方針
育成就労制度は、改正法の公布日である2024年6月21日から起算して3年以内に施行されます。
まだ、正確な日程は決まっていません。最新の情報は出入国在留管理庁などのWebサイトで発表される予定です。主務省令(具体的な手続きなどの詳細)についても同様で、十分な準備期間をもって検討が進められています。
技能実習制度の見直しについては複数回の有識者会議が行われ、2023年11月30日に最終報告書が関係閣僚会議へ提出されました。
技能実習生はいつまで受け入れられる?
海外からの技能実習生の受け入れは、改正法の施行日までに技能実習計画の認定をし、施行日から3ヶ月を経過するまでに実習を始めていれば可能です。
技能実習制度から育成就労制度への円滑な移行を目的に、2030年までは2つの制度が同時に運用されます。
技能実習生は今後どうなる?
改正法の施行日までに日本に来日している技能実習生は、そのまま技能実習を続けられます。
技能実習1号を持つ技能実習生が2号に移行することは可能ですが、2号から3号への移行は一定の範囲に制限される見込みです。詳細は今後発表されますが、3号への移行ではなく特定技能制度への移行が進められていくでしょう。
参照元:出入国在留管理庁「育成就労制度・特定技能制度Q&A」
育成就労制度とは
そもそも、技能実習の代わりに創設される育成就労制度とはどのような制度なのでしょうか。
ここでは、いまいち概要が掴めていない方のために、育成就労制度が創設された背景や基本的な内容を解説します。
育成就労制度が創設された理由
育成就労制度が創設される背景には、技能実習制度であった制度の建前と実像のギャップを解消する目的があります。
技能実習制度は、元々「海外の人材への技能移転」という国際貢献が目的の制度でした。しかし実際には、人手が不足している企業の労働力確保の手段として機能しているのが実状です。
そこで、政府が実態と現場のニーズから検討した結果、「労働力を受け入れるための制度」として育成就労制度の創設が決まりました。
また、育成就労制度の創設には技能実習制度であった「転職ができない」「悪質なブローカーの存在」といった問題を解消するという目的もあります。
育成就労制度の基本提言
ここでは、育成就労制度の基本提言を解説します。内容を読めば、技能実習制度からどのような点が変わるか分かるでしょう。
なお、育成就労制度の正式な内容や詳細はこれから決められます。施行までに変更点がある可能性も踏まえ、参考としてご覧ください。
制度の位置付け
育成就労制度の目的は、「人材確保」と「人材育成」です。 3年間の育成期間で外国人人材を「特定技能1号」の水準まで育成し、日本の人手不足の業界で活躍してもらうことを目指します。
技能実習制度でも、2号まで優良に修了した技能実習生は特定技能への移行が可能です。育成就労制度は、より特定技能制度で働く外国人を増やすことに焦点が当てられた制度といえるでしょう。
対象分野と人材育成機能
育成就労制度の対象とはなる分野は、技能実習制度の対象職種・作業を引き継ぐわけではありません。育成就労制度で新たに分野を設けます。なお、特定技能制度への移行が前提になっているため、特定産業分野と同じ分野になる予定です。
働ける分野も、特定技能の業務区分と同一にし、主たる技能を決めて育成や評価を進めます。
受け入れ見込み人数
受け入れ人数については、事業所ごとの人数ではなく分野ごとに見込み人数を決める予定です。人数は、受け入れ状況や情勢などを考慮し柔軟に判断されます。
育成就労制度の転籍について
技能実習制度では、「やむを得ない場合」を除いて転籍(転職)が認められていませんでした。育成就労制度では、「やむを得ない場合」の範囲を拡大したうえ、基準も明確にします。加えて、以下の条件を満たせば、自分の意思での転籍も可能です。
- 同じ場所で1年以上働いている
- 技能試験および日本語能力A1相当の試験に合格する
- 同じ業務区分内で転籍する
監理団体やハローワークなどが転職支援を実施します。
監理・支援・保護
監理団体(監理支援団体)は、企業と密接な関係のある役職員の監理への関与を制限し、外部監査人を設置します。それにより、独立性や中立性をより強める予定です。
また、外国人技能実習機構(外国人育成就労機構)では特定技能外国人の相談業務も追加し、より支援や保護に力を入れます。
特定技能制度への移行
育成就労制度から特定技能制度への移行は、以下の基準が条件になります。
- 技能検定試験3級または特定技能1号評価試験合格
- 日本語能力A2相当以上の試験合格
なお、制度開始後しばらくの間は、上記に相当する講習の受講でも移行が認められる見込みです。
試験に不合格の場合、再度受験をするために「育成就労」の在留資格の1年延長が認められます。
国や自治体の役割
国や自治体、外国人育成就労機構が連携し、適切な受け入れや雇用ができる体制を目指します。
制度の所管省庁である出入国在留管理庁は制度運用の中心的役割、各分野の所管省庁はガイドラインやキャリアプランの作成などが役割です。
送り出し機関
育成就労制度では、二国間取決め(MOC)を締結している国からのみ、外国人を受け入れます。悪質な送り出し機関やブローカー介入の取り締まりが目的です。
また、送り出し機関への支払い手数料を抑え、外国人と雇用企業が分担して払う仕組みができます。これにより、外国人が来日前に多くの借金を抱えるケースを防げるでしょう。
日本語能力
外国人が日本での生活や業務にスムーズに適応するには、日本語能力の向上が必要です。育成就労制度では、段階的に日本語能力を向上させるべく以下の基準を設けます。
- 就労開始前にA1相当以上の試験(日本語能力試験N5など)合格または相当講習受講
- 特定技能1号移行時にA2相当以上の試験(日本語能力試験N4など)合格 ※相当講習の受講も可
- 特定技能2号移行時にB1相当以上の試験(日本語能力試験N3等)合格
引き続き日本で働くためには、日本語能力を上げていかなければならない仕組みです。
また、企業が優良認定を受ける条件に「日本語教育に力を入れている」といった内容が含まれます。
参照元:出入国在留管理庁「育成就労制度の概要」
育成就労制度と技能実習制度の違い
育成就労制度と技能実習制度の各項目の違いは、以下のとおりです。
| 育成就労制度 | 技能実習制度 | |
| 制度の目的 | ・人材育成 ・人材確保 | ・人材育成 ・国際貢献 |
| 転職 | 条件を満たせば可能 | 原則不可 |
| 対象職種 | 16分野 | 91職種168作業 |
| 在留期間 | 原則3年 (再試験で1年延長可能) | 最長5年 |
| 関係機関 | 監理支援機関 | 監理団体 |
| 在留資格 | 育成就労 | ・技能実習1号 ・技能実習2号 ・技能実習3号 |
| 日本語要件 | あり | 介護職種以外はなし |
※分野や職種の数は2025年8月時点
人材確保を目的に外国人を雇用できること、そして対象職種が変わる点が特に大きな変更点といえます。
現在、技能実習を実施している場合は、どのような点が変わるか把握しておきましょう。
育成就労制度のメリット・デメリット
技能実習制度で問題になっていた点を解消し、内容を進化させた育成制度は、利用するメリットの多い制度です。しかし、企業側の視点で見るとデメリットともいえる部分も。良い点と悪い点の両方を知り、制度を利用するのか、それとも通常の外国人雇用を進めるのか検討しましょう。
育成就労制度で外国人を雇用するメリット
育成就労制度で外国人を雇用すると、長期的な雇用がしやすくなります。 育成就労制度は特定技能制度への移行が前提になっているため、技能実習制度からの移行よりも手続きがスムーズに進むでしょう。
特定技能1号の在留期間は最長5年、2号に移行すれば更新の制限はありません。2号へ移行すると、将来的に永住権取得の道も開けます。すべての分野で2号に移行できるわけではありませんが、ほとんどの分野で長期的な雇用が可能になるというのは、大きなメリットといえるでしょう。
また、日本語能力が高い人材を雇用できるのもメリットの一つ。育成就労制度で入国し、継続して働き続けるには日本語能力を段階的に高めて行かなくてはなりません。外国人の学習意欲もその分高まるので、日本語レベルが向上しやすくなります。
育成就労制度で外国人を雇用するデメリット
育成就労制度では、外国人が自分の意思で転籍することが可能です。1年以上働いていれば転籍が許可されるので、時間を掛けて雇用した外国人が短期間でほかの企業に移ってしまう可能性があります。そのため、転籍リスクを減らす取り組みをしなければなりません。
また、育成就労制度では、技能実習制度よりも企業側の費用負担が増えると考えられます。今まで、外国人が負担してきた費用の一部が、企業負担になるためです。また、新たに日本語教育支援に掛かる費用なども追加されます。
外国人の負担を軽減し人権に配慮し、より日本で働きやすくするためには必要なことです。しかし、企業にとってはデメリットともいえるでしょう。
まとめ
育成就労制度は、改正法の公布日である2024年6月21日から起算して3年以内に施行されます。正式な日付はまだ未定ですが、今から情報収集を行い、いつから始まっても良いよう準備をしておきましょう。
育成就労制度の詳細はこれから決定されます。将来的に育成就労制度の利用を検討している企業の方は、出入国在留管理庁のWebサイトで最新情報をチェックしてみてください。

サービスを運営する中でよく伺うお悩みや質問に対して、真摯に向き合いながらも、分かりやすく、すぐに役立つコンテンツ発信を目指しています。





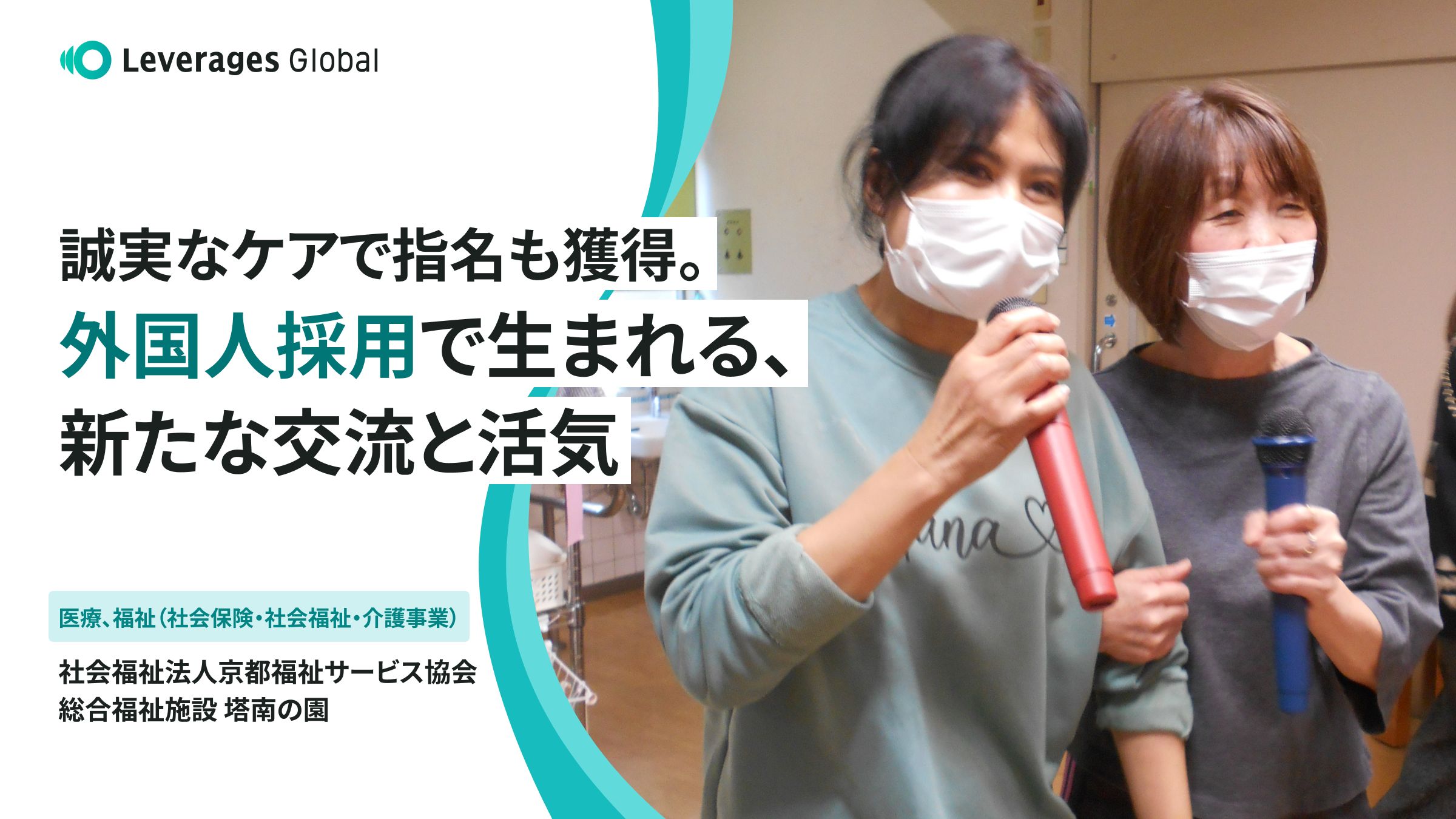
.png)





