
執筆: Leverages Global編集部 (ライター)
ネパール人スタッフと一緒に働く中で、宗教や文化の違いに戸惑った経験はありませんか?これからネパール人の採用を検討している場合、宗教的・文化的背景を理解しておくことはとても重要です。 ネパールでは国民の約8割がヒンドゥー教を信仰し、その教えは生活の隅々にまで根付いています。 この記事では、ネパールの宗教事情や文化的なタブーを解説。また、ネパール人スタッフと円滑な関係を築き、いきいきと働いてもらうためのポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
※本稿は「人種」や「国籍」といった特定の属性に対するイメージを単純化する意図はありません。本稿の内容は、あくまでインドネシアの文化や社会通念を紹介するものであり、個々人の性格は多種多様であるという点を踏まえてご覧ください。
外国人採用ならLeverages Global
外国人採用をもっと安心で簡単に、
はじめてみませんか?
支援実績多数!レバレジーズグローバルが支持される理由は、
以下サービス概要資料からご確認ください。
ネパールの基本情報
宗教について知る前に、まずはネパールがどういった国なのかを知っておきましょう。
| 面積 | 14.7万平方キロメートル |
| 人口 | 2,969万4,614人 |
| 首都 | カトマンズ |
| 民族 | パルバテ・ヒンドゥー、マガル、タルー、タマン、ネワール等 |
| 言語 | ネパール語 |
南アジアに位置するネパールは、北は中国、南はインドという2つの大国に挟まれた内陸国です。国土面積は約14.7万平方キロメートルで、日本の北海道の約1.8倍。国土の北側には、世界最高峰のエベレストを含む雄大なヒマラヤ山脈が連なっています。首都は国内最大の都市であるカトマンズです。
気候は国土の標高差が非常に大きいため、南部の亜熱帯気候から北部の高山気候まで極めて多様です。首都カトマンズ周辺は日本と同じように四季があり、全体としては6月から9月が雨季、10月から5月が乾季に分かれます。
ネパールの特徴は多言語国家であることです。公用語のネパール語のほか、国内には120以上の多様な言語が存在します。また、英語教育を行っている学校もあり、英語を話せる人は少なくありません。
参照元:外務省「ネパール基礎データ」
関連記事:ネパール人スタッフに聞く!国民性や仕事観【宗教上のタブーも解説】
ネパールで信仰されている宗教とは?
ネパールは、多様な宗教が共存する多宗教国家として知られています。外務省「ネパール基礎データ」によると、ネパールにおける宗教の割合は以下のとおりです。
| ヒンドゥー教 | 81.3% |
| 仏教 | 9% |
| イスラム教 | 4.4% |
ネパール国民の81.3%がヒンドゥー教徒です。そのため、社会や文化の基盤にはヒンドゥー教の教えが深く根付いています。次に多いのが仏教徒で人口の9%です。この2つの宗教は、ネパールの人々の精神的な支柱となっています。
さらに、イスラム教徒が4.4%いるほか、キラント教(ムンドゥム教)という土着の民族宗教を信仰する人々も。そして、キリスト教徒も少数ながら見られます。
ネパールの宗教における大きな特徴は、ヒンドゥー教と仏教が対立することなく穏やかに共存している点です。一つの寺院に両方の神仏が祀られていることも珍しくありません。このように、さまざまな信仰が互いの文化に影響を与えながら、ネパール独自の宗教観を形成しているのです。
以下では、ネパールにおけるヒンドゥー教・仏教・イスラム教について解説します。
ヒンドゥー教
ネパールで最も多くの人々が信仰しているのがヒンドゥー教です。ヒンドゥー教は、生命は何度も生まれ変わるという「輪廻転生」の思想を根幹に持ち、非常に多くの神々を信仰する多神教であることが大きな特徴です。
人々の暮らしの中には、神聖な動物とされる牛を食べないという食文化があります。また、左手は「不浄の手」と考えているため、物の受け渡しや食事の際に左手を使うことはありません。
なお、かつて社会の基盤であったカースト制度は法律で禁止されましたが、人々の意識の中には今もその考え方が残っている場合があります。カースト制度は非常にデリケートな問題であり、個人の背景を理解する上で知っておきたい知識の一つです。
仏教
ネパールは、仏教の創始者である釈迦(ブッダ)の生誕地「ルンビニ」がある国として、世界中の仏教徒にとって特別な意味を持つ場所です。国民の9%が仏教を信仰しており、ヒンドゥー教に次ぐ規模を誇ります。
ネパールの仏教が持つ際立った特徴は、ヒンドゥー教との強い結びつきです。長い歴史の中で2つの宗教は互いに影響を与え合っており、仏教の神様とヒンドゥー教の神様が同じ場所で祀られていることも珍しくありません。また、地理的に近いチベットからの影響も大きく、特にヒマラヤ山岳地帯ではチベット仏教が広く信仰されています。たとえば、カトマンズにある仏塔「ボダナート」は、チベット仏教の重要な聖地の一つです。
このように、ネパールの仏教は多様な要素を取り入れながら、人々の生活の一部として深く根付いています。
イスラム教
ネパールにおいて、イスラム教はヒンドゥー教、仏教に次いで3番目に信者の多い宗教です。
イスラム教徒(ムスリム)は、イスラム教の教えに則った生活様式を大切にしています。なかでも、特に知られているのが食生活に関する決まりごとです。豚肉やアルコール類を口にしないハラールの習慣は、生活の基本となります。また、1日に5回、聖地メッカの方角を向いて礼拝を行う習慣も。そのほか、イスラム暦の9月には「ラマダン」と呼ばれる約1ヶ月間の断食を行います。
ネパール全体で見ると少数派かもしれませんが、ムスリムにとってこれらの宗教的習慣は非常に重要です。
参照元:外務省「ネパール基礎データ」
宗教に関連するネパールのお祭り
ネパールでは、ヒンドゥー教や仏教を中心に、多くの宗教行事や祭りが行われています。祭りは単なる年中行事ではなく、神々へ感謝や祈りを捧げ、家族や地域社会との絆を再確認する非常に大切な機会です。ネパール人と働く際は、彼らが祭りをとても重要視していることを知っておくと良いでしょう。
特に国全体で祝われる大きなお祭り期間中は、多くの人が故郷へ帰省します。日本の正月やお盆のように、家族と過ごすために長期の休暇を希望することがあるかもしれません。
ここでは、宗教に関連するネパールのお祭りを5つ紹介します。相互理解を深めるためにも、祭りの文化的・宗教的な背景を知っておきましょう。
ダサイン
ダサインは、ネパールで最も盛大に祝われている国民的なお祭りです。9月~10月頃に約15日間にわたって行われます。日本の正月やお盆のように多くの人が故郷に帰り、家族や親戚と共に過ごします。
ダサインは、ヒンドゥー教の女神ドゥルガーが水牛の姿をした悪魔マヒシャを打ち負かしたという伝説にもとづき、善が悪に勝利したことを祝うものです。期間中、人々は新しい服を着て、家の掃除や装飾を行います。また、年長者によって額に米やヨーグルト、赤い粉を混ぜた「ティカ」を付けてもらい、健康や幸福への祝福を受けます。
ティハール
ティハールは、ダサインに次いでネパールで2番目に大きなお祭りです。「光の祭り」としても知られ、10月~11月頃に5日間にわたって開催されます。
ティハールでは、富と繁栄をもたらす女神ラクシュミーを家に迎えるため、家々を季節の花であるマリーゴールドやイルミネーションで美しく飾ります。また、人間だけでなく、カラスや犬といった動物たちにも感謝を捧げ、崇拝するのが大きな特徴です。最終日には兄弟姉妹の絆を祝い、お互いの長寿と健康を祈る「バイ・ティカ」という儀式を行います。
ホーリー
ホーリーは、春の訪れを祝う色鮮やかなお祭りです。「色彩の祭り」として世界的に有名で、2月~3月頃の満月の日に行われます。
ホーリーはヒンドゥー教のクリシュナ神の伝説に由来し、悪に対する善の勝利を象徴しています。当日は友人や家族、見知らぬ人同士でも、色粉や色水をかけ合って楽しみます。年齢や社会的地位に関係なく誰もが参加し、街中がカラフルな笑顔で溢れる、非常に陽気でエネルギッシュなお祭りです。
シヴァ・ラートリー
シヴァ・ラートリーは、ヒンドゥー教の三大神の一人である破壊と創造の神「シヴァ神」の生誕を祝うお祭りです。2月~3月頃の新月の前夜に行われます。
この日は国内最大のヒンドゥー教寺院であるカトマンズのパシュパティナート寺院に、ネパール中はもちろん、インドからも多くの信者やサドゥー(ヒンドゥー教の修行者)が集まります。信者たちは断食をしたり、夜通し祈りを捧げたりして、シヴァ神への信仰を示します。熱心なヒンドゥー教徒にとって、非常に神聖な一夜です。
インドラ・ジャトラ
インドラ・ジャトラは、首都カトマンズで盛大に行われるお祭りの一つです。8月~9月頃に8日間にわたって開催されます。
インドラ・ジャトラは雨と豊穣の神であるインドラに感謝を捧げるもので、モンスーンの終わりと収穫期の始まりを告げます。最大の見どころは、生き神とされる少女「クマリ」やガネーシャ、バイラヴの神々の山車がカトマンズの旧市街を練り歩く様子です。カトマンズ盆地に住むネワール族にとって特に重要なお祭りで、多くの人々が伝統的な音楽や踊りに参加し、街全体が熱気に包まれます。
ネパールにおける宗教・文化上のタブー
ネパール人と円滑な関係を築くためには、彼らが大切にしている宗教的・文化的な習慣やタブーを理解し、尊重する姿勢が欠かせません。日本では当たり前の行為が意図せず相手を不快にさせてしまう可能性があるので、注意が必要です。
ここでは、特に注意したい4つのポイントを紹介します。
牛肉は食べない(牛は神聖な生き物)
ネパールで大多数を占めるヒンドゥー教徒にとって、牛はシヴァ神の乗り物として崇拝される神聖な動物です。そのため、牛肉を食べることは宗教上の大きなタブーとされています。ネパール国内で牛肉はあまり流通しておらず、食べる習慣がありません。
社員食堂のメニューはもちろん、懇親会のお店選びの際には牛肉が含まれていないかを確認しましょう。鶏肉や羊肉、ヤギ肉は食べられることが多いですが、個人の食習慣は異なるため、本人に直接確認するのが賢明です。
左手で食事をする・物を渡すのはNG
ヒンドゥー教の文化では、右手は「清浄な手」、左手は「不浄の手」とされています。したがって、食事をする際や書類・名刺など物の受け渡しをする際には、右手を使うのがマナーです。
左手で物を渡す行為は、相手に対して失礼にあたると受け取られる可能性があります。両手を使うのは問題ありませんが、もし左手しか使えない状況の場合は、「左手で失礼します」と一言添える心遣いが大切です。
他人が口をつけたものを共有しない
ネパールではヒンドゥー教の「浄・不浄」の観念から、他人が口をつけたものは穢れたものと見なされます。そのため、他人が一度口をつけた食べ物や飲み物を共有する習慣がありません。
ネパール人は、日本で行われるペットボトルの回し飲みや大皿に盛られた料理を各自の箸で取る行為に抵抗を感じるでしょう。食事会などでは、取り分け用の箸やスプーンを用意するなどの配慮が必要です。
他人の頭を触ってはいけない
ネパールでは、頭は「体の中で最も神聖な部位」であり、魂や神が宿る場所と考えられています。そのため、他人の頭に触れることは非常に失礼な行為と見なされるのです。
日本では子どもを可愛がったり後輩を褒めたりする際に、親しみを込めて頭をなでることがあります。しかし、こうした行為は相手の尊厳を傷つけることになりかねないため、たとえ相手が子どもであっても避けるべきです。
ネパール人と円滑に働くには
ネパール人は多様な文化の中で育っているため適応力が高く、仕事にも真摯に取り組む人が多いといわれています。しかし、日本とは異なる価値観や習慣を持っているため、円滑な関係を築くには彼らの文化的背景を理解し、尊重する姿勢が不可欠です。
ここでは、ネパール人スタッフと共に働くうえで心掛けたいポイントを3つ解説します。
文化の違いを理解する
ネパール人と働くうえで最も重要なのは、宗教や文化の違いを受け入れることです。特に大多数が信仰するヒンドゥー教の教えは、彼らの生活の隅々にまで根付いています。
たとえば、神聖な動物である牛を食べない、不浄とされる左手で物の受け渡しをしないといった習慣は、その代表例です。食事会や懇親会を企画する際は、こうした食文化に配慮したメニュー選びが求められます。
頭ごなしに日本の常識を押し付けるのではなく、「なぜ日本ではそうするのか」「ネパールにおける文化ではどうなのか」といった視点を持つことが、信頼関係を築く第一歩となるでしょう。
時間の大切さを伝える
ネパールには「ネパリタイム」という言葉があるように、時間に対して比較的おおらかで、約束の時間に多少遅れることをあまり問題視しない文化があります。これは悪気があるわけではなく、日本とは異なる時間感覚が背景にあるためです。
そのため、日本のビジネスシーンで求められる時間厳守の重要性については、丁寧に伝える必要があります。なぜ時間を守る必要があるのかを、「チーム全体の業務スケジュールに影響が出る」「お客様との信頼関係に関わる」といった具体的な理由を論理的に説明しましょう。感情的に叱るのではなく、日本の職場文化として根気強く教える姿勢が大切です。
家族と過ごす休暇に配慮する
ネパール人は家族との絆を非常に大切にします。特に「ダサイン」のような大きなお祭りは、日本の正月やお盆休みのように、多くの人が故郷に帰って家族と過ごすための重要な期間です。
そのため、お祭りに合わせた長期休暇や帰国の希望には、できる限り柔軟に対応しましょう。家族を想う気持ちを尊重する姿勢は、本人のモチベーションや会社への帰属意識を高め、人材の長期的な定着にもつながります。
関連記事:「外国人との異文化コミュニケーションに必要なこと|心構えや失敗例も」
まとめ
ネパールは、ヒンドゥー教と仏教が穏やかに共存する珍しい宗教文化を持つ国です。ネパール人の生活習慣や価値観は、こうした宗教の教えに深く関係しています。
ネパール人と共に働くうえでは、牛を神聖視する食文化や左手を不浄とする考え方、頭に触れないといった文化上のタブーへの配慮が欠かせません。また、「ダサイン」のような大きなお祭りを家族と過ごすことを非常に大切にするため、長期休暇への理解も重要です。
もちろん、ここで紹介した特徴がすべてのネパール人に当てはまるわけではありません。大切なのは文化的な背景を理解し尊重しつつも、一人ひとりの個人と向き合うことです。相互理解を深める姿勢が、良好な職場環境と信頼関係の構築につながるでしょう。
ネパール国籍の方をはじめ、外国人採用をもっと安心で簡単に進めてみませんか? 外国人採用支援実績多数のLeverages Globalでは、貴社に合ったサポートが可能です。人材のご紹介やマネジメントに関するご相談でもお気軽にお問い合わせ下さい。

サービスを運営する中でよく伺うお悩みや質問に対して、真摯に向き合いながらも、分かりやすく、すぐに役立つコンテンツ発信を目指しています。


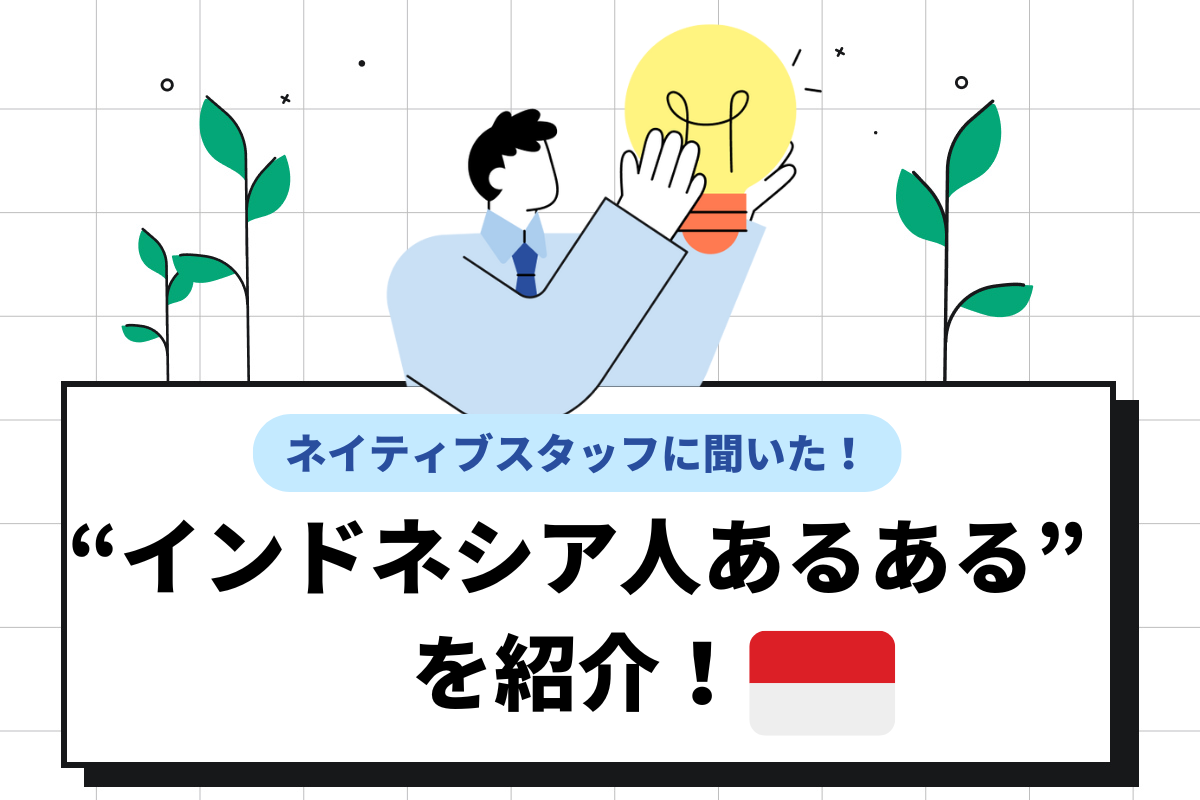


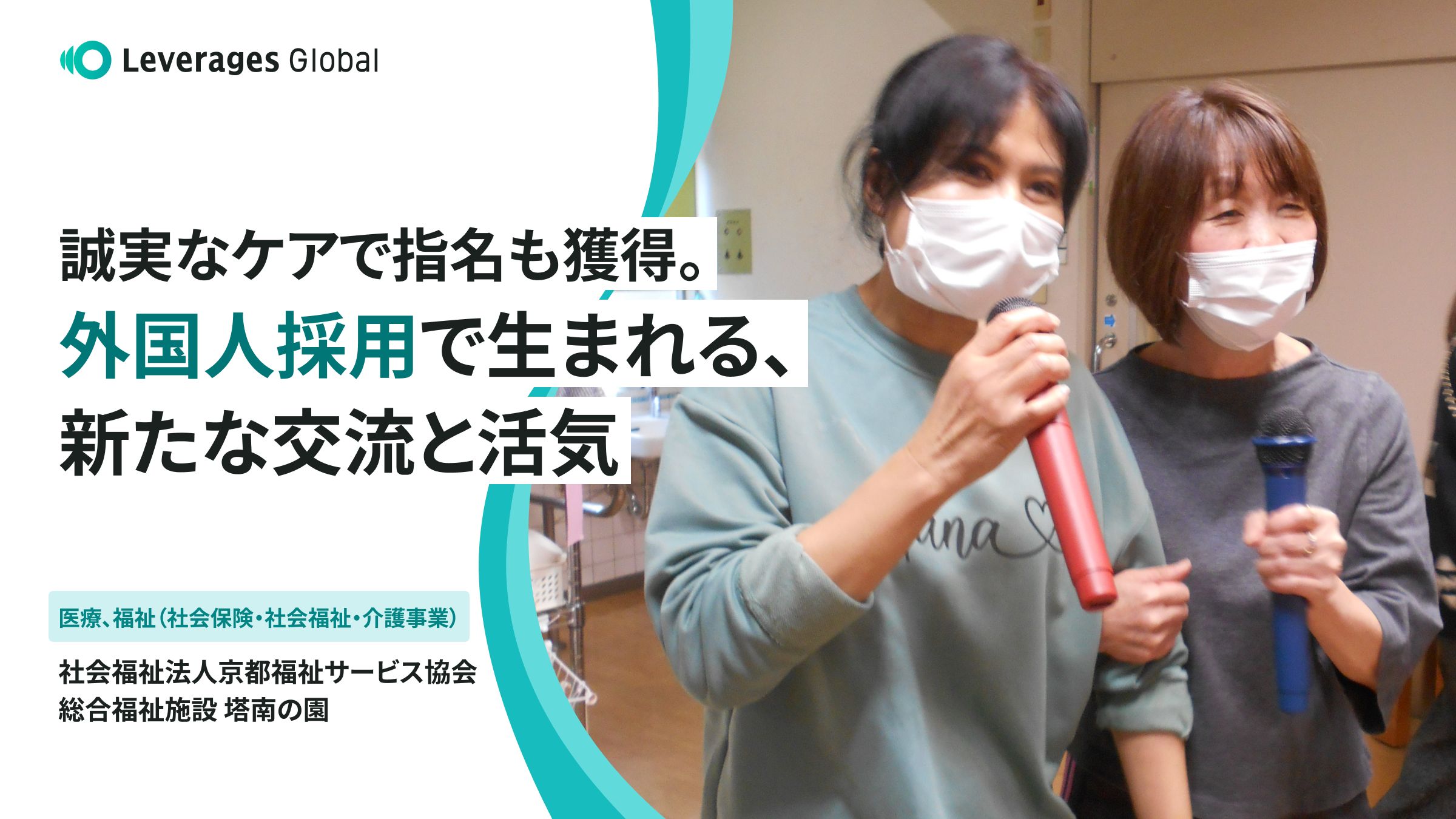
.png)




