
執筆: Leverages Global編集部 (ライター)
監修: 濱川 恭一 (行政書士)
BJTビジネス日本語能力テストと日本語能力試験(JLPT)のどちらを採用に活用すべきか、お悩みの担当者の方もいるかもしれません。
採用基準に設定する試験を選ぶ際は、測定する能力だけでなく受験者数を考慮するのが大切です。受験者が多く一般的な試験であれば、外国人が応募しやすいでしょう。
この記事ではBJT・JLPT・EJUの比較やテストの概要について紹介。日本語能力試験を採用に使う際に気をつけるべきポイントやレベルの目安なども解説しています。
外国人採用ならLeverages Global
外国人採用をもっと安心で簡単に、
はじめてみませんか?
支援実績多数!レバレジーズグローバルが支持される理由は、
以下サービス概要資料からご確認ください。
BJT・JLPT・EJUの比較【初めてでも分かる】
はじめに「BJTビジネス日本語能力テスト」「日本語能力試験(JLPT)」「日本留学試験(EJU)」の概要を、以下の表で確認しておきましょう。
| 日本語検定の名前 | 運営団体 | 実施頻度 | 特徴 |
| BJTビジネス日本語能力テスト | 日本漢字能力検定協会 | ほぼ毎日 | ビジネスコミュニケーション能力を測る試験 |
| 日本語能力試験 (JLPT) | ・国際交流基金 ・日本国際教育支援協会 | ・1年に2回(※実施回数が少ない海外の都市もある) ・2024年は7月・12月 | さまざまな場面を想定した総合的な試験 |
| 日本留学試験 (EJU) | 日本学生支援機構 | ・1年に2回 ・2024年は6月・11月 | 日本の大学への入学希望者を対象に、日本語力と基礎学力を測る試験 |
BJTビジネス日本語能力テストは、日本特有の言葉遣いや行動などのビジネスコミュニケーション能力を測る試験です。日本語の基礎知識があることを前提に、情報処理能力やビジネススキルを測定します。
日本語能力試験は、日本語の知識や実際の運用能力などの観点から総合的に言語コミュニケーション能力を測る試験です。毎年多くの人が試験を受けており、2023年の受験者数は120万人を超えました。外国人の日本語能力を測定する指標として最も一般的だといえます。
企業の採用基準とするには、基本的に日本語能力試験を選ぶのがおすすめです。BJTビジネス日本語能力テストを基準に設けている企業は多くありません。受験者数も例年1万人程度であり、日本語能力試験より少ないため、必須要件にすると候補者がかなり限られてしまうでしょう。
BJTビジネス日本語能力テストは、内定者に入社前の学習として勉強してもらう目的としては良い試験です。詳しくは「BJTビジネス日本語能力テスト」の項目で説明しているので、あわせてご覧ください。
なお、日本留学試験は大学入学希望者が対象になる試験であり、企業が採用基準に使うことは基本的にありません。
参照元: 日本語能力試験公式Webサイト「日本語能力試験とは」 日本語能力試験公式Webサイト「過去の試験のデータ」 日本学生支援機構「日本留学試験(EJU)」 日本学生支援機構「スケジュール(試験日)」
日本語能力試験(JLPT)
日本語能力試験は国際交流基金と日本国際教育支援協会が主催する、世界最大規模の日本語試験です。英語表記の「Japanese-Language Proficiency Test」が略され、「JLPT」とも呼ばれます。日本語能力の測定に加え、企業の採用基準や在留資格を申請する要件などにも使われている試験です。
2023年には92の国と地域で試験が実施され、約126万人が受験しました。受験者数が多いため、自社の採用基準として設定すれば外国人が応募しやすいメリットがあるでしょう。
JLPTのレベル
日本語能力試験は日本語の知識(文字・語彙・文法)と読解、聴解の3要素で構成されています。試験はマークシート方式で実施され、会話や作文能力を直接測る問題はありません。
5段階のレベル(N5〜N1)があり、数字が小さいほど合格難易度は高まります。つまり、N1が最も難しく、N5が最も易しいレベルです。
ここでは、各レベルに合格している外国人の日本語能力の目安を紹介します。
N1
N1は、さまざまな場面で使われる日本語が理解できるレベルです。N1の合格者は、新聞の論説や評論などを読み、文章構成や内容の把握が可能です。小説を読んで、登場人物の心情やストーリー展開の理解ができる外国人も多くいます。
また、自然な速さのニュースや会話を聞き、話の展開や内容、人の関係性などの詳細な理解や要旨の把握が可能です。
N1は最高難易度であり、高度な会話が必要な業務や日本語の資料作成なども任せられるでしょう。幅広い分野の仕事で活躍が期待できるレベルです。
N2
N2はビジネスレベルといわれています。日常生活で使われる日本語に加え、より幅広い場面で使用される日本語が一定程度分かるレベルです。
N2の合格者は新聞や雑誌の記事、分かりやすい評論などであれば、内容が把握できます。敬語が使われた正式な文章が理解できる外国人も少なくありません。
また、日常生活に限らずさまざまな場面で、自然に近い速さの会話やニュースを聞き、話の展開や内容、人の関係性の理解や要旨の把握が可能です。職場の会議で話の展開が理解できる外国人も多くいます。
社外の人に商談やプレゼンを行う業務は難易度が高いといえますが、社内では基本的に問題なくやり取りできるでしょう。接客業で雇用する場合は、接客にとどまらず外国人アルバイトの教育やメニューの翻訳なども任せられます。
N3
N3は日常的なシーンで使用される日本語を一定程度理解できるレベルです。流暢な会話は難しいですが、意思の疎通には問題がないでしょう。
N3の合格者は、日常的なテーマについて具体的な内容が書かれた文章を理解できます。日常生活で目にする少し難しい文章は、表現を言い換えれば要旨を把握することが可能です。
また、日常生活でやや自然に近い速さの会話を聞き、人の関係性などとあわせて具体的な内容をほとんど理解できます。
接客業で雇用する場合は、敬語表現や定型文のマニュアル化が必要です。なお、N3で習得する漢字数は小学4年生の終了段階で学んでいる数より多くありません。漢字を読む機会が多い業務では、ふりがなを振ったりすぐにサポートできる環境を整えたりする必要があります。
接客業務の経験がある外国人のなかには、自然な日本語が使える人もいるでしょう。面接で実際の会話能力を判断するのが大切です。
N4
N4は基礎的な日本語が理解できるレベルです。日本で生活できる最低限の日本語能力がある水準といえます。
合格者は、基礎的なことばや漢字が使われていれば、日常生活の身近なテーマについて書かれた文章を理解することが可能です。また、日常的な場面で少しゆっくりと会話が行われれば、内容をほとんど把握できます。
N4レベルの外国人と話すときは、複雑な構文を使わずに「~を~します。~してください」と端的に話しましょう。相手が聞き取れるよう、話す速度を遅くすることも大切です。また、外国人が分かる漢字は少ないため、マニュアルには必ずふりがなを振るようにしましょう。
任せる業務は日本語の使用頻度が少ない単純労働が適しているといえます。ただし、日本語の指示が伝わらない可能性があるため、翻訳アプリを使ってサポートするのがおすすめです。
N5
N5は、基礎的な日本語を一定程度理解できるレベルです。合格者は、日常会話で頻出するあいさつや表現などが分かったり、ごく簡単なコミュニケーションが取れたりします。
ひらがなやカタカナ、日常生活で使われるごく基本的な漢字で書かれた文章の理解が可能です。また、日常生活でよく経験する場面で短い会話がゆっくり話されれば、必要な情報が聞き取れます。
N5の合格者は日本語の勉強を始めたばかりの人も多く、雇用する場合は日本語教育研修の時間をしっかり確保することが重要です。日本語のみで会話するのは難しいため、単純労働を任せる場合も通訳できる従業員が職場に必要でしょう。
外国人特化の人材紹介サービス「WeXpats」では、求職者の日本語レベルを把握したうえで企業様にご紹介しています。そのほか、在留資格や関連手続きについてもご相談いただけるので、外国人採用が初めてのご担当者さまにも安心してご利用いただくことが可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。
JLPTを基準に外国人を採用する際の注意点
日本語能力試験を活用すれば外国人の日本語能力の目安が分かるものの、会話や作文能力は測れないことに注意しましょう。接客や資料作成などの業務が多い場合は、自社で作成した試験や面接などで、外国人に必要な能力があるか別途確認するのがおすすめです。
また、応募者の外国人を評価する際は日本語能力だけでなく、職務を行える経験やスキルなどがあるかもチェックしましょう。日本語レベルが高いからといって、業務を行う能力も高いとは限りません。
そのほか、能力のある応募者を見落としてしまうケースにも注意が必要です。仕事の能力が十分でコミュニケーションに問題がない外国人を、求めている日本語能力試験の基準に満たないからと不採用にしてしまう企業は多くあります。N1などの高いレベルにこだわらず、応募者自身を総合的に評価するのが大切です。
参照元: 日本語能力試験公式Webサイト「過去の試験のデータ」 日本語能力試験公式Webサイト「N1~N5:認定の目安」
JLPTの合格証明書の読み方
JLPTの合格証明書を見る際は、総合得点だけでなく、言語知識・読解・聴解の「区分別得点」も確認することが重要です。これにより、その人の日本語能力の特性をより正確に把握できます。
JLPTの合否は総合得点で決まりますが、同じ「合格」でもレベルには幅があります。例えば、最も難しいN1レベルでは180点満点中100点、最も易しいN5レベルでは180点満点中80点が合格基準点です。そのため、合格基準点ぎりぎりで合格した人と、満点に近い得点で合格した人では、実際の日本語運用能力に差があると考えられます。
さらに、区分別の得点を見ることで、その人の得意・不得意な分野がわかります。「言語知識(文字・語彙・文法)」「読解」「聴解」の3つの区分がありますが、全ての区分でバランス良く得点している人もいれば、特定の区分だけが突出して高い(あるいは低い)人もいます。例えば、「会話は流暢(聴解は高得点)だが、文章を読むのは苦手(読解は低得点)」といったケースも少なくありません。総合得点と合わせて区分別得点を確認することで、より具体的な日本語スキルを理解する手がかりとなります。
日本語能力試験(JLPT)と名称が似ている日本語教育能力検定試験
日本語能力試験(JLPT)と名称が似ていますが、「日本語教育能力検定試験」という全く異なる試験が存在するため注意が必要です。この試験は、日本語学習者の能力を測るJLPTとは目的が異なり、日本語を教える能力を認定するための試験です。
この「日本語教育能力検定試験」は、日本語教師としての知識や能力を測るもので、2024年度からは国家資格である「登録日本語教員試験」に移行しました(※経過措置あり)。
非常に稀ですが、外国人の中にもこの日本語教育能力検定試験(あるいは新しい登録日本語教員試験)に合格している人がいます。日本語を母語としない人に日本語を教える能力が認められているわけですから、その場合、JLPT N1合格や、ビジネス場面での日本語能力を測るBJTビジネス日本語能力テストでハイスコアを持つ人よりも、さらに高いレベルの日本語運用能力を持っていると判断できるでしょう。求人応募者の資格欄などで見かけた際は、JLPTと混同しないようにしましょう。
BJTビジネス日本語能力テスト
BJTビジネス日本語能力テストは、ビジネスシーンにおける日本語コミュニケーション能力を測る試験です。日本漢字能力検定協会が運営しており、在留資格の認可要件としても使われています。実施方法は、試験会場にあるコンピューターで解答するCBT(Computer Based Testing)方式です。
テストは国内外で行われていますが、受験者は日本語能力試験より多くありません。受験者の多くは中上級程度の日本語力を持っています。そのため、採用基準にすると候補者が限られてしまう可能性もあります。評価基準として使うのではなく、内定した外国人に入社前に学習してもらうのがおすすめです。
BJTビジネス日本語能力テストでは、日本語のビジネス環境を想定した場面が出題されます。情報処理能力やビジネススキルが測定できるため、内定者のビジネスコミュニケーション能力向上に活かせるでしょう。外国人に学習を進めてもらう際には、勉強や受験にかかる費用を補助することが大切です。
BJTを採用基準にするメリット
先述のとおり、BJTビジネス日本語能力テストは受験者数がそれほど多くないため、採用基準ではなく内定者の学習に活用するのがおすすめです。
しかし、ビジネス場面での日本語の運用能力が高い人材を雇用したい場合、BJTビジネス日本語能力テストで応募者を評価するのも有効でしょう。日本語やビジネスの知識があることを前提に、実践力も測れる試験だからです。
ただし、応募者が限られてしまうのを避けるため、必須要件ではなく歓迎要件として募集するのを推奨します。
BJTのレベル
BJTビジネス日本語能力テストは聴解テスト、聴読解テスト、読解テストの3パートで構成されています。
試験の結果は800点までのスコアと得点数に応じたレベルで評価されるのが特徴です。レベルはJ5(日本語でビジネスコミュニケーションをほとんど行えない水準)から、J1+(どんなビジネスシーンでも日本語で十分にコミュニケーションできる水準)まで6段階あります。
J1+
J1+は、600~800点のスコアレベルです。
J1+の合格者は、どんなビジネスシーンでも日本語で十分にコミュニケーションできる能力があります。会議や商談などで相手の話を正確に把握でき、どんなビジネス文書も正しく理解することが可能です。
J1
J1は、530~599点のスコアレベルです。
J1の合格者は幅広いビジネスシーンにおいて、日本語で適切にコミュニケーションできる能力があります。会議や商談などでは、相手の話がだいたい理解できるレベルです。ビジネス文書は、日常的なものであれば正確に把握できます。
J2
J2は、420~529点のスコアレベルです。
J2の合格者は限られたビジネスシーンであれば、日本語で適切にコミュニケーションが取れます。会議や商談では相手の話が一定程度分かり、日常的なビジネス文書がおおむね把握できるレベルです。
普段のビジネス会話はだいたい理解できますが、日本語の運用能力や知識に一部問題があり意思疎通がうまくいかないこともあります。
J3
J3は、320~419点のスコアレベルです。
J3の合格者は限られたビジネスシーンで、日本語のコミュニケーションが一定程度取れます。また、少しであれば会議や商談で相手の話を理解することが可能です。日常的なビジネス文書も基本的なものに限り、一定程度把握できます。
普段のビジネス会話は簡単なものがだいたい理解できますが、日本語の運用能力や知識には問題があり、意思疎通がうまくいかないことが多いレベルです。
J4
J4は、200~319点のスコアレベルです。
J4の合格者は限られたビジネスシーンで、最低限のコミュニケーションが取れます。日常的なビジネス文書は基本的なものに限り、断片的に理解することが可能です。
ゆっくりした速さの簡単なビジネス会話はだいたい把握できます。しかし、日本語の運用能力や知識には問題が多々あり、意思疎通が難しいことがあるレベルです。
J5
J5は、0~199点のスコアレベルです。
J5の合格者は日本語でほとんどビジネスコミュニケーションを行えません。ゆっくりした速さの簡単な会話が、部分的に理解できる程度です。
日本留学試験(EJU)
日本留学試験は日本学生支援機構が運営する試験で、留学生を対象に日本の大学で必要とされる能力の測定を目的としています。その趣旨から、あえて企業が採用基準に設定する必要性は低いでしょう。
しかし、自社の求人に応募してきた留学生が、日本留学試験の成績しか持っていない場合もあるかもしれません。どのような試験か、事前に概要を把握しておきましょう。
EJUは日本語能力と基礎学力を測る試験
日本留学試験では一般的な日本語試験とは違い、日本語能力だけでなく基礎学力も測ります。具体的には、日本語のほか、理科(物理・化学・生物)・総合科目・数学が試験科目です。このなかから、大学などが受験者に受けてもらう科目を指定します。
日本語の科目では大学などでの勉強や生活に必要な言語能力の測定を目的としており、試験構成は読解、聴解・聴読解、記述の3領域です。記述試験では、掲示された考え方に対しての自分の意見や、ある問題についての現状や将来の予想、解決方法などについて論じます。
参照元: 日本学生支援機構「日本留学試験(EJU)とは」 日本学生支援機構「日本留学試験の実施要項」
まとめ
応募者の採用基準には、受験者数が多い日本語能力試験を設定しましょう。BJTビジネス日本語能力テストは評価基準ではなく、内定した外国人に学習してもらう活用方法がおすすめです。
それぞれの日本語試験の特徴を活かし、自社の目的に応じて利用するようにしましょう。

サービスを運営する中でよく伺うお悩みや質問に対して、真摯に向き合いながらも、分かりやすく、すぐに役立つコンテンツ発信を目指しています。






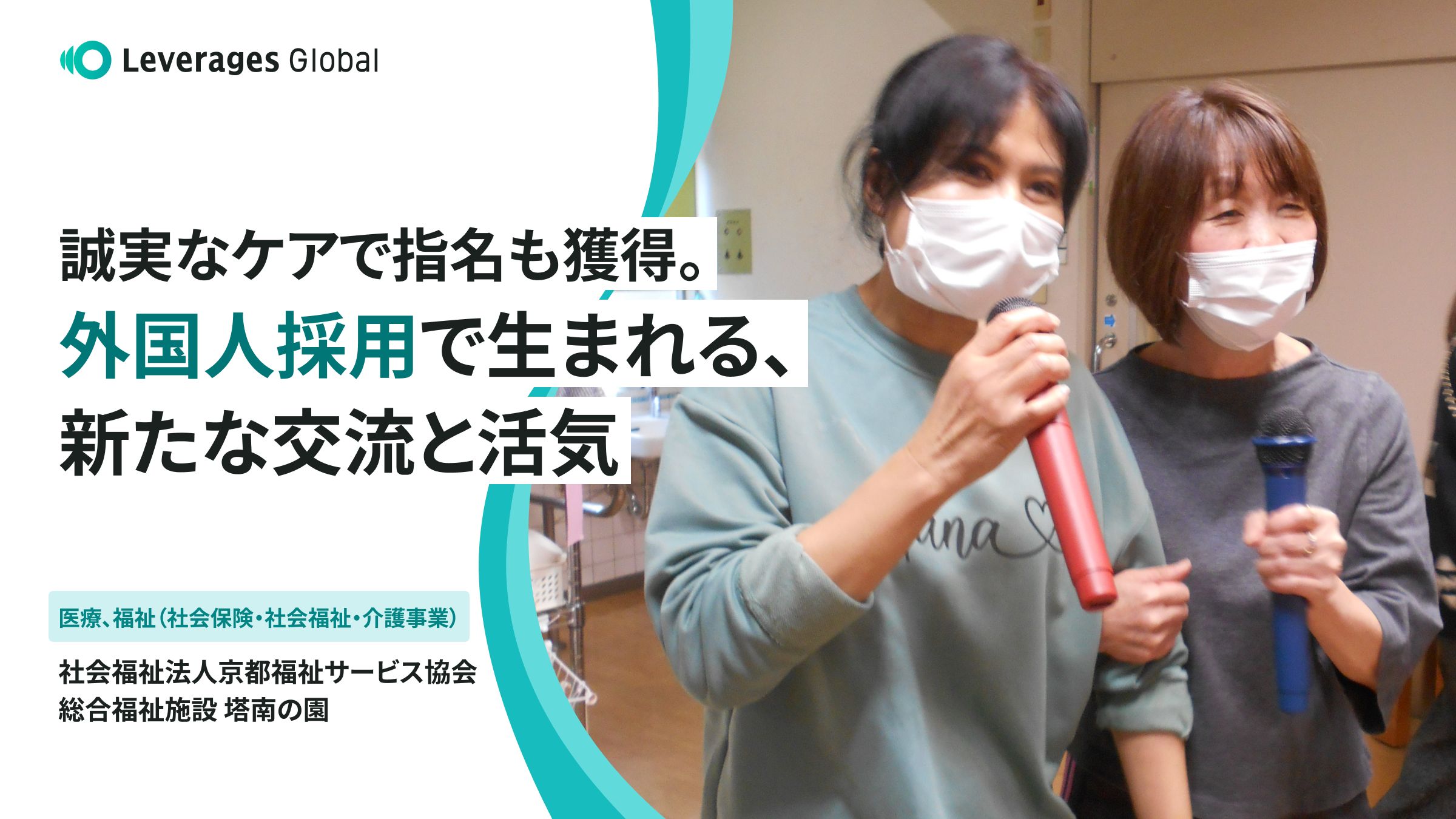
.png)





